
カスタマーハラスメントとは何か?
サービス業を中心に「カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)」という言葉を耳にする機会が増えています。これは顧客や取引先などの“外部”から、企業の従業員に対して行われる理不尽な要求や威圧的な言動など、ハラスメント行為全般を指します。
カスハラの典型的な例
– 店舗やコールセンターで怒鳴る・暴言を吐く– 担当者の変更を過剰に要求
– 法外な金銭要求や土下座の強要
– 社員のSNSアカウントを特定し、嫌がらせを行う
– 口コミサイトやSNSで一方的に攻撃し企業にダメージを与える これらはすべて、従業員が通常の業務範囲を超えた負担を強いられるものであり、精神的ストレスの原因となります。なかには、カスハラによりうつ病を発症し、離職に至るケースもあります。
社会背景としての“顧客第一主義の行き過ぎ”
長年にわたり、日本社会では「顧客は神様」「お客様の声はすべて正しい」といった考え方が根付いてきました。その結果、企業も従業員も「多少理不尽でも耐えるべき」といった空気に覆われてきました。しかし時代は変わりつつあります。 働き手の確保が難しくなる中で、従業員を大切にする企業こそが選ばれる時代へ。カスハラ問題は、単なる接客のトラブルではなく、「組織のあり方」そのものを問う問題なのです。
カスハラが企業に及ぼすリスク
カスハラは単なる個人トラブルではなく、組織全体に深刻な影響を及ぼします。実際に発生した際のリスクを正しく把握しておくことが、経営上のリスクマネジメントにも直結します。
(1)精神的ストレスによる生産性の低下
厚生労働省の調査によると、カスハラを受けた従業員の多くが「誰にも相談できなかった」「我慢するしかなかった」と回答しています。相談しづらい環境では、ストレスが蓄積し、心身の健康に悪影響を及ぼします。集中力や判断力の低下、感情の不安定さが業務全体の質を下げ、他のスタッフにも悪影響が波及します。(2)優秀な人材の流出と人手不足の加速
特に若手社員や女性従業員は「自分の身は自分で守れない」と感じた職場から早期に離職する傾向が強く、貴重な人材が流出してしまいます。また、カスハラリスクが高い業種(小売、外食、医療、宿泊など)では慢性的な人手不足が続いており、研修に投資して育てた人材が辞める損失は大きな経営課題です。(3)職場の士気・組織風土の悪化
カスハラに遭遇した仲間を企業が守らなかったという事実は、チーム全体の信頼を損ねます。「自分も同じ目に遭っても助けてもらえない」と感じると、職場全体が萎縮し、発言や提案が出にくい閉鎖的な雰囲気が蔓延します。これはチーム力の低下を招き、イノベーションや改善活動の停滞にもつながります。(4)企業イメージの毀損と訴訟リスク
SNSや口コミサイトなどの発達により、対応を誤れば一気に「炎上」する時代です。たとえば、カスハラを受けた従業員がSNSで「会社に相談したが放置された」と投稿すれば、企業側が加害者とみなされる危険すらあります。また、労災申請や訴訟に発展すれば、法的コストやブランド価値の毀損は計り知れません。
社員を守るための「企業の対応責任」
もはや「現場任せ」では済まされない時代です。企業として、明確な対応方針と仕組みを持つことが、社員の安心につながります。
(1)厚労省ガイドラインと対策マニュアルの活用
厚生労働省は2020年に『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』を公開し、企業に対し以下の取り組みを推奨しています。 – カスハラの定義を明確にする– 社内ルールや対応フローを整備する
– 管理職に対応訓練を行う
– 被害者が安心して相談できる窓口を設ける これらは法的義務ではないものの、実施している企業ほど従業員満足度が高い傾向にあります。
(2)対応ルールを全社員に周知・徹底
「カスハラと判断した場合は対応を中断してもよい」「内容によっては上長や本部に即時報告」といった具体的な行動基準を共有することで、現場は萎縮せず対応できるようになります。(3)管理職が“盾”になる意識を持つ
現場の社員が顧客対応に追われている中で、管理職が迅速に介入し、現場を守ることが信頼構築の鍵になります。対応を一任するのではなく、「困ったら私が出ます」という姿勢が組織風土を大きく変えるのです。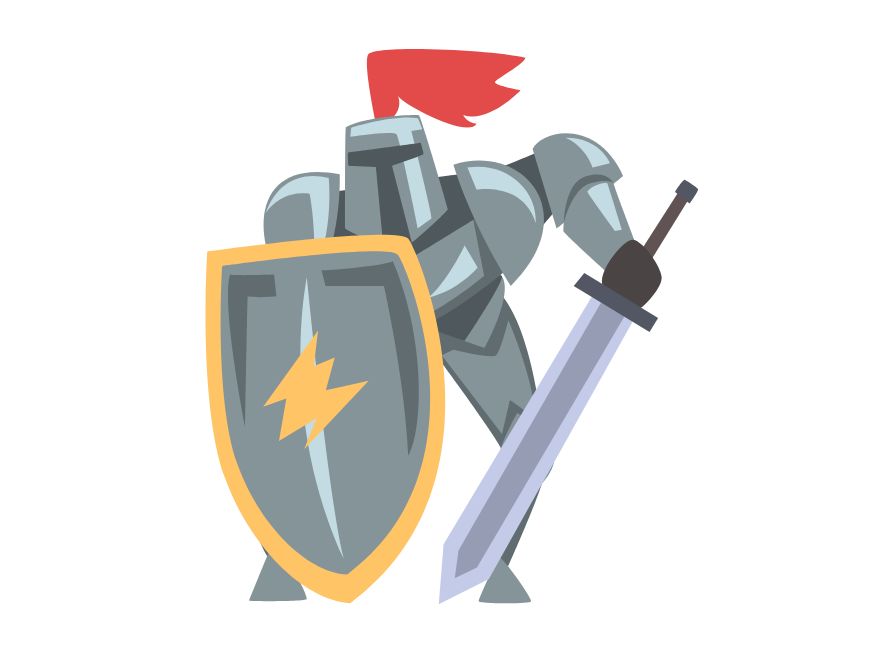
カスタマーハラスメント研修の導入事例と効果
「方針を作るだけ」では不十分です。最も重要なのは、現場の社員一人ひとりが「自分自身の身を守る行動ができる」状態になること。そこで必要となるのが、実践的なカスハラ対応研修の導入です。 【導入目的】
– カスハラの定義や判断基準を理解し、恐れずに対応できるようにする
– 正当な顧客対応と、許容すべきでない言動の線引きを明確にする
– 組織として対応する姿勢を全社員に共有する 【研修内容の一例】
(1)カスハラの判断演習
参加者に複数の事例を提示し、「これはクレームか?ハラスメントか?」をグループで判断。
→ グレーゾーンの難しさを認識し、判断力を養いましょう。 (2)対応スクリプトの習得
「申し訳ありませんが、それはお受けできかねます」など、対応用の“断り文句”や“報告フレーズ”をロールプレイ形式で練習。
→ 実際の現場でも即座に活用できる実践力をつけましょう。 (3)ケース別の対応フローの確認
暴言・土下座強要・SNSでの誹謗など、種類ごとの対応ルールや報告経路を確認し、研修中に記録として残す。
→ トラブル時に迷わず行動できるようになるはずです。
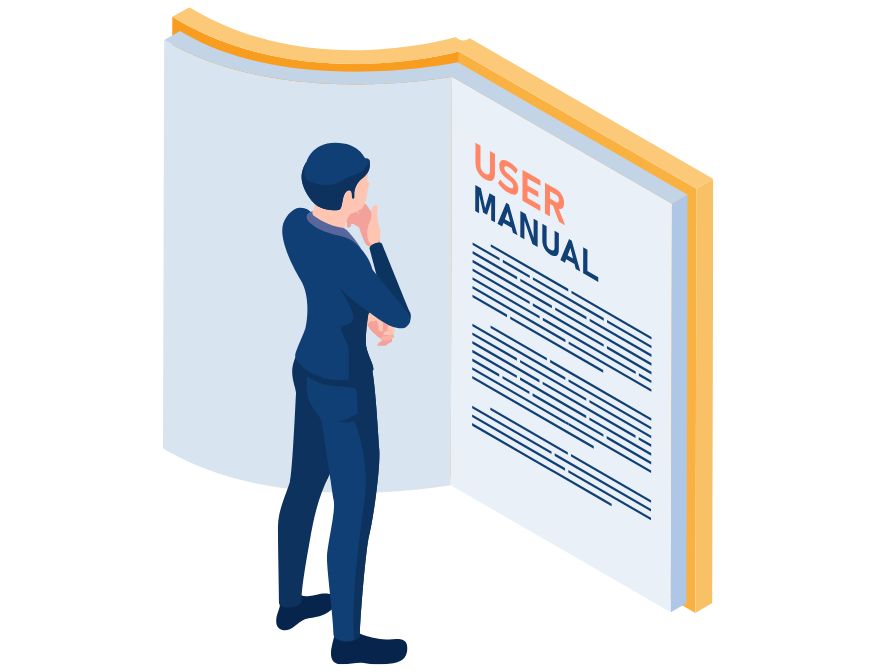
研修をより効果的にする工夫
単に「知識を伝える」だけでは、研修の効果は一過性に終わります。そこで、実際の企業研修では、“体験型・参加型”を取り入れることが有効です。
(1)ビジネスゲームやカード教材の活用
例:カスハラ対応カードゲーム「守れ!現場のヒーロー」– 10種以上の「カスハラ事例カード」を各チームに配布
– 対応カード(断り方、報告、上長同行、記録)から正しい行動を選択
– 最も“適切な対応”が多いチームに得点
→「体験しながら学ぶ」形式により、記憶に残りやすく、現場応用もしやすくなる
(2)メンタルヘルスやレジリエンス研修と連携
カスハラを完全に防ぐことはできません。だからこそ「受けた後にどう回復するか」も含めて、ストレスマネジメントやレジリエンス(心の回復力)を組み合わせる研修が効果的です。 【研修の組み合わせ例】– 午前:カスハラ対応演習
– 午後:ストレスケア法、相談・支援制度の紹介、リフレクション
→ 知識+内省+対処法の三本柱で「折れにくい現場」を作る
(3)フォローアップの設計
一度の研修で終わらせず、1〜3ヶ月後に簡易テストやグループワークを設けると、「学んだだけ」で終わらない定着を図ることができます。 – チェックシート記入-対応マニュアルの再確認
-eラーニングで再視聴可能にするなども有効です。
まとめ:これからの「顧客第一」と「社員第一」の両立に向けて
これまで企業は「顧客満足」を最重要指標としてきました。しかし時代は変わり、「社員を守れる企業こそ、顧客から選ばれる」という価値観が広がっています。 今後、求められるのは「顧客第一」か「社員第一」かの二択ではなく、その両立をどう図るかというバランス感覚です。 – 顧客に対しては「誠実に対応するが、理不尽には毅然と対応する」
– 社員に対しては「困った時は必ず会社が味方になる」と言える体制づくり カスハラ対策の強化は、単なるトラブル予防ではなく、企業の信頼を育む人材戦略です。社員が安心して働ける環境を整えることは、結果として接客品質や顧客ロイヤルティの向上にもつながります。 「うちの会社は、社員を守る」――この言葉を自信を持って掲げられる企業が、これからの時代を生き抜く強さを持つのです。
【執筆者情報】
ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃
研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。

