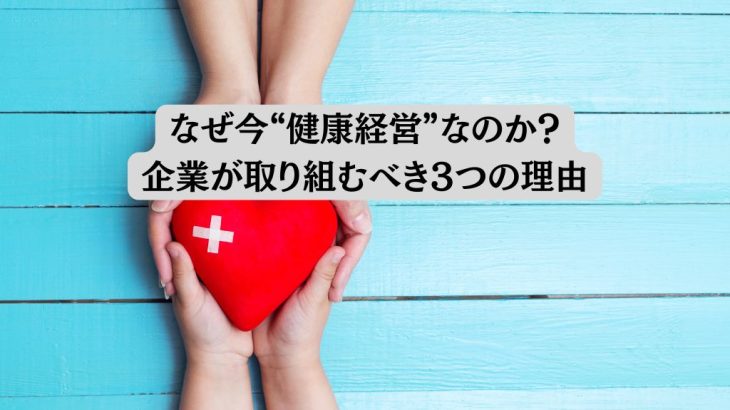健康経営に取り組むべき理由① 生産性向上とパフォーマンス最大化
企業にとって最も基本的で、かつ重要な課題の一つが「生産性の向上」です。限られた人材と時間のなかで最大の成果を生み出すことは、どの業界・業種でも共通する永遠のテーマといえるでしょう。そのカギを握るのが、実は「社員一人ひとりの健康状態」なのです。
健康と業務パフォーマンスの密接な関係
表面的には元気に働いているように見える社員でも、慢性的な疲労や生活習慣病の兆候を抱えている場合があります。また、メンタル不調を抱えながら無理をして出勤しているケースも少なくありません。これらは「見えにくい不調」として放置されがちですが、実際には業務効率を大きく下げ、組織全体の生産性に直結しています。 例えば「プレゼンティーズム」という概念があります。これは欠勤(アブセンティーズム)とは異なり、社員が出勤しているにもかかわらず、体調不良やストレスなどにより本来の力を十分に発揮できない状態を指します。調査によれば、プレゼンティーズムによる経済的損失は欠勤による損失を上回るとも言われており、企業にとって見えないコストの代表例です。頭痛や腰痛、睡眠不足、花粉症といった身近な症状であっても、集中力や判断力の低下につながり、結果的に大きな生産性損失を生んでいるのです。健康投資の効果は「見える化」できる
健康経営の重要なポイントは、単に「社員の健康を守る」という情緒的な話ではなく、その効果を「経営指標」に落とし込めることです。例えば、生活習慣病の予防施策に取り組んだ結果、医療費の削減だけでなく欠勤日数が減少し、年間で数千万円規模の効果が出た企業もあります。また、ストレスチェックやメンタルヘルス研修を継続的に実施したことで、休職者数が減り、業務の引き継ぎや再配置に伴う人件費の圧縮につながったケースも報告されています。 さらに、健康投資は「攻めの経営」にも直結します。集中力や創造性の高い社員が増えることで、新しいアイデアが生まれやすくなり、組織全体のパフォーマンスが底上げされるのです。単に「病気を防ぐ」だけではなく、「最高の状態で働ける社員を増やす」ことこそが健康経営の真の価値といえるでしょう。身近な施策の積み重ねが大きな差を生む
では、具体的に企業はどのような施策を取ればよいのでしょうか。難しい仕組みを導入する必要はありません。例えば以下のような取り組みは、多くの企業で実践可能です。 ✔運動機会の提供:オフィスに簡単なストレッチタイムを導入、歩数競争アプリを利用してチーム対抗イベントを実施✔食生活の改善支援:社員食堂でのヘルシーメニュー提供、栄養バランスを考慮した弁当の補助
✔睡眠改善の啓発:睡眠セミナーや社内キャンペーンを通じ、質の高い休養を取る習慣を推進
✔メンタルケア:定期的なストレスチェックとフォローアップ面談、オンラインカウンセリングの導入 これらの施策は単体で見ると小さな取り組みに思えるかもしれません。しかし、組織全体で積み重ねることで「健康に配慮された職場文化」を醸成し、社員のパフォーマンス向上を後押しします。
生産性向上は企業競争力に直結する
グローバル競争が激化する中、単に「長時間働く」ことで成果を出す時代はすでに終わりました。むしろ、限られた時間で高い成果を出す社員をどれだけ増やせるかが、企業の競争力を左右します。ここで問われるのは、「社員が本来の能力を発揮できる環境を提供しているか」という視点です。 健康経営はまさに、その環境整備の根幹をなすものです。社員が心身ともに健康であればあるほど、集中力、判断力、コミュニケーション力が向上し、それが売上や利益の向上に直結します。つまり、生産性向上の出発点は「社員の健康」という最もシンプルで普遍的な要素にあるのです。
健康経営に取り組むべき理由② 離職防止と採用力アップ
健康経営が注目される背景には、「人材の流動化」「採用難」「離職率の高さ」といった労働市場の変化もあります。社員が心身の健康を維持しながら働ける環境を整えることは、単に福利厚生の充実にとどまらず、人材戦略の中核を担う施策といえるのです。
健康経営とエンゲージメントの相関関係とは
従業員が「会社から大切にされている」と感じると、仕事へのモチベーションやエンゲージメントが高まることが、多くの調査で示されています。健康診断やメンタルヘルスサポートなどの仕組みを用意するだけでなく、「本気で社員の健康を守る」という姿勢を経営層が明確に打ち出すことで、従業員は「この会社で長く働きたい」という気持ちを強めます。 逆に、社員の健康に無関心な企業はどうでしょうか。過重労働やメンタル不調が放置され、安心して働けないと感じれば、優秀な人材ほど早々に退職してしまいます。特に人手不足が慢性化する今の時代、一人の離職がチーム全体に大きな影響を与えるリスクは見過ごせません。離職防止の具体的効果
健康経営を実践することで、実際に離職率が下がった事例も多く見られます。例えば、ストレスチェックの活用や早期面談体制を整備した結果、長期休職者が大幅に減少した企業では、離職率も安定的に低下しました。さらに、社員が体調を崩して長期休職に入る前にフォローできる体制を整えることで、「キャリアを断念せざるを得ない」という事態を防ぎ、長期的な人材定着につなげています。 このような仕組みを整えることは、社員一人ひとりの人生を支えるだけでなく、採用・教育にかかるコスト削減にも直結します。新たな人材を採用し、育成するには多大な時間と費用がかかります。その投資を繰り返さなくて済むことは、経営効率の観点からも極めて大きなメリットです。採用市場での競争力強化
健康経営は、採用活動においても強力なアピールポイントになります。特にZ世代やミレニアル世代は、「給与」や「安定性」だけでなく、「働きやすさ」や「自分らしさを大切にできる職場環境」を企業選びの基準にしています。 例えば、健康経営優良法人の認定を受けた企業は、求人広告や採用イベントで「社員を大切にする企業」としてのイメージを強く打ち出すことができます。これは単なるラベルではなく、企業の姿勢を象徴する証明書のような役割を果たします。結果として、応募数が増えるだけでなく、「この会社なら安心して働ける」と感じる質の高い人材を惹きつける効果も期待できます。 さらに、健康経営は社内外のブランディングにも貢献します。「社員の健康を重視する企業」という評価は、顧客や取引先に対しても安心感を与え、信頼関係の強化につながるのです。つまり、採用力の向上と企業ブランドの向上は表裏一体であり、その中心に健康経営が存在するといえるでしょう。Z世代の価値観とマッチする健康経営
近年、採用市場の主役となりつつあるZ世代は、働くことに対して「お金」よりも「ウェルビーイング(心身の健康と充実)」を重視する傾向があります。リモートワークやワークライフバランスを当然視する彼らにとって、健康経営に取り組んでいる企業は「自分たちの価値観に合った会社」として映ります。 例えば、オンラインカウンセリング制度や、ワークアウト支援などを導入する企業は、Z世代にとって魅力的に映ります。これは、ただの福利厚生ではなく、「社員の声を聴き、時代に即した働き方を整えている」ことの証明だからです。結果として、他社との差別化が図れ、採用の場面で優位性を築くことができます。 このように、健康経営は単なる健康支援にとどまらず、社員のエンゲージメントを高め、離職を防止し、さらには採用力や企業ブランドの向上に直結します。人材こそが企業の競争力を決定づける時代において、「健康への投資」は最も効果的で持続可能な人材戦略なのです。
健康経営に取り組むべき理由③ 企業価値・社会的評価の向上
健康経営の意義は、社員のパフォーマンス向上や採用・定着だけにとどまりません。さらに広い視点で見れば、企業の社会的評価やブランド価値を高める強力な手段となります。近年、投資家や社会全体の関心が「財務情報」から「非財務情報」へとシフトするなかで、健康経営はまさにその中心的なテーマのひとつに位置づけられているのです。
健康経営と人的資本経営の接点
2023年から「人的資本の情報開示」が義務化され、企業は従業員数や離職率、研修機会、ダイバーシティ推進などの情報を積極的に開示する必要が生じました。ここで注目されるのが、従業員の健康維持・増進にどれだけ取り組んでいるかという点です。 企業の持続的成長を考えるうえで、人材は最大の資本です。その人材が健康でなければ、どんな戦略も成果につながりません。逆にいえば、「社員の健康を守り、働きやすい環境を提供している企業」という事実は、投資家にとっても「安定した成長が見込める企業」と映ります。ESG投資・株主からの評価
ESG(環境・社会・ガバナンス)投資が拡大する中で、「社会(Social)」の項目として健康経営は重要視されています。社員の健康を軽視する企業は、短期的な利益追求に偏っていると評価され、投資家から敬遠される可能性すらあります。一方、健康経営に積極的に取り組む企業は、「長期的に持続可能な経営を行っている」と認識され、株主や市場からの評価を高めやすいのです。 また、健康経営優良法人の認定や、社外アワードの受賞は、単なるPRにとどまらず、株主や金融機関にとっての安心材料となります。これは資金調達の円滑化や株価の安定といった、経営基盤の強化にもつながります。
CSRからSDGsへの広がり
社会的責任(CSR)の観点からも、健康経営は大きな意味を持ちます。企業は従業員だけでなく、その家族や地域社会に対しても影響を及ぼします。社員が健康に働き続けられることは、家庭や地域の安定にも直結し、結果として地域社会への貢献度を高めるのです。 さらに、SDGs(持続可能な開発目標)の観点からも、健康経営は「目標3:すべての人に健康と福祉を」「目標8:働きがいも経済成長も」に合致しています。企業が健康経営を推進することは、国際的な社会課題の解決に寄与していることを示すものであり、その取り組みが社会的評価を高めることは言うまでもありません。ブランド力の向上と好循環
健康経営を推進する企業は、「社員を大切にする企業」として社会から好意的に受け止められます。これは顧客にとっての安心感につながり、取引先との関係強化にも直結します。例えば、健康経営優良法人の認定を取得した企業が「安心・信頼のブランド」として選ばれやすくなり、競合との差別化に成功したケースも少なくありません。 また、こうした社会的評価は社内にも波及します。「自分が働いている会社は社会から評価されている」という誇りやロイヤリティが高まり、従業員のモチベーション向上や離職防止にもつながります。つまり、健康経営は「社会的評価の向上→ブランド力強化→社員の誇り向上→さらに社会的評価が高まる」という好循環を生み出すのです。 このように、健康経営は単なる社内施策にとどまらず、企業の社会的評価やブランド価値を高める戦略的取り組みです。人的資本経営、ESG投資、SDGsといった世界的潮流と結びつけることで、企業は長期的に持続可能な成長を実現できるのです。
まとめ
本コラムでは、企業が今まさに「健康経営」に取り組むべき3つの理由を整理してきました。第1に、社員一人ひとりの健康状態が生産性や業務パフォーマンスに直結し、見えにくいコストであるプレゼンティーズムや欠勤による損失を防ぐことで、組織全体の力を底上げできる点。第2に、社員の健康を守る姿勢がエンゲージメントを高め、離職防止や採用力強化につながり、特にZ世代の価値観に合致することで人材確保に優位性を生み出す点。そして第3に、健康経営は人的資本経営やESG投資、SDGsと密接に結びつき、企業の社会的評価やブランド価値を高め、持続可能な成長を実現する点です。 こうして振り返ってみると、健康経営は「コスト」ではなく「投資」であることがはっきりと見えてきます。むしろ、社員の健康に投資しないことこそが、将来的に大きな損失を招くリスクになり得るのです。健康で意欲的に働ける社員が増えれば、その成果は売上や利益といった財務指標だけでなく、組織文化や社会的評価といった非財務的価値にも波及します。 もちろん、健康経営を推進するには時間もコストも必要です。しかし、その第一歩は必ずしも大掛かりな施策である必要はありません。例えば「定期的なストレッチタイムの導入」や「健康診断後のフォローアップ面談」、「オンラインカウンセリングの試験導入」といった、小さな取り組みからでも十分に始められます。重要なのは、経営層が「社員の健康を経営課題として本気で捉えている」という姿勢を打ち出し、社内文化として根付かせることです。 健康経営は、企業の未来を形づくる基盤です。生産性の向上、人材の定着・獲得、社会的評価の強化という3つの観点から、「なぜ今取り組むべきなのか」は明白です。これからの時代、健康経営を戦略の中に組み込み、持続可能な成長を実現できるかどうかが、企業の明暗を分けることになるでしょう。
【執筆者情報】
ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃
研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。