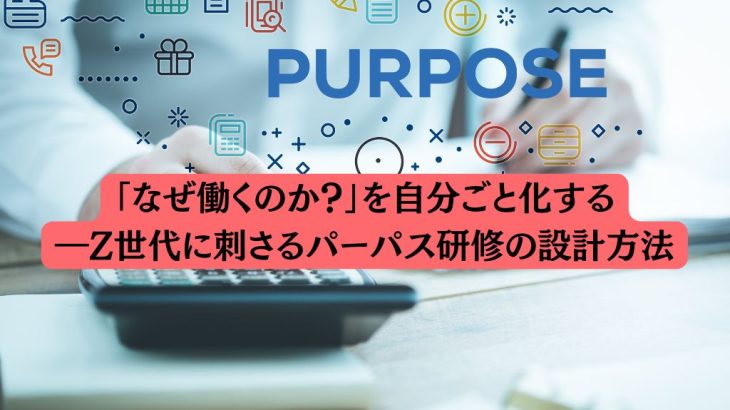Z世代が働く目的を重視する理由
Z世代が就業観において大きな特徴を持つのは、「なぜ働くのか?」という問いを、非常にリアルに、そして切実に考えている点です。従来の世代が「安定した収入」や「昇進・キャリアアップ」を中心にキャリアを描く傾向があったのに対し、Z世代は仕事そのものに「意味」や「社会的意義」を求めます。彼らにとって働くことは単なる生活の糧ではなく、自分の人生観や価値観と深く結びついた営みであり、「目的」がなければ長期的なモチベーションを維持することは難しいのです。
■ デジタルネイティブとしての背景
Z世代は生まれたときからインターネットが当たり前に存在する環境で育ち、SNSを通じて常に世界とつながってきました。日常的に他人の価値観やライフスタイルに触れ、社会課題や多様な働き方の存在を知っています。そのため、「仕事=生活費を稼ぐ手段」という発想にとどまらず、「自分の仕事は社会にどんなインパクトを与えるのか?」「自分らしい生き方にどうつながるのか?」といった問いを持ちやすいのです。これは、終身雇用や年功序列を前提に働いてきた世代とは大きな違いです。■ 「意味のある仕事」を求める姿勢
従来世代は「やりがい」よりも「安定」を優先し、組織に属することでキャリアを形成してきました。しかしZ世代は、たとえ安定性が高くても「意味を感じられない仕事」には長く留まりません。自分の成長や社会貢献を感じられる環境を重視し、場合によっては短期間で転職することもいとわないのです。実際、Z世代の離職率が高い理由のひとつは「企業の価値観と自分の価値観が一致しない」ことにあります。■ パーパスを「自分ごと化」できるかどうかがカギ
このように「目的志向」が強いZ世代にとって、企業が掲げる理念やパーパスは単なるスローガンではなく、「自分の価値観と重なるかどうか」が重要になります。もし企業パーパスが抽象的で、現場の社員が自分の経験や思いと結びつけられなければ、共感は得られません。逆に、パーパスを自分の言葉で語れるようになると、仕事の意味づけが強まり、モチベーションやエンゲージメントが高まります。 つまり、Z世代が働く目的を重視する背景には、デジタルネイティブとしての情報環境、社会課題への関心の高さ、そして自己実現欲求の強さがあります。彼らにとって「なぜ働くのか?」は避けて通れない問いであり、この問いに企業が誠実に向き合えるかどうかが、エンゲージメントや定着率を左右するのです。
パーパス研修の必要性とその目的とは
Z世代が「働く目的」を重視する背景を踏まえると、従来の「理念浸透研修」だけでは不十分であることが明らかになります。多くの企業では、経営理念やビジョンを社員に理解してもらう取り組みを行ってきました。しかし、それは経営層が一方的に伝える「トップダウン型」になりがちで、Z世代の社員にとっては「押し付けられた言葉」に聞こえてしまうことが少なくありません。そこで必要となるのが「パーパス研修」です。これは理念を“伝える”のではなく、社員が「自分の言葉で語れるようになる」ことを目的とした研修であり、Z世代の価値観と強く親和性を持ちます。
■ 単なる理念浸透研修との違い
理念浸透研修が「会社が大切にしている価値観を知ること」に焦点を当てているのに対し、パーパス研修は「社員一人ひとりが自分の人生観と企業の存在意義を結びつけること」を重視します。つまり、企業が提示するパーパスをそのまま覚えるのではなく、「なぜ自分はこの会社で働くのか?」という問いを通じて、自らの価値観と接点を見つけることに意味があります。この点で、パーパス研修はZ世代が求める「主体的な学び」と相性が良いのです。■ Z世代が共感しやすい「橋渡し」としての役割
Z世代は自己理解を重視する傾向がありますが、同時に「社会や企業にどう役立てるか」を探しています。パーパス研修は、この「自己理解」と「企業理解」をつなぐ“橋渡し”の役割を担います。 ✔ 自分の価値観を言語化することで、仕事に対する意味づけが強化される✔ 企業のパーパスをストーリーや事例を通して理解し、自分の経験と照らし合わせられる
✔ 結果として「自分はこの会社で何を実現できるのか」という納得感を得られる このようなプロセスは、単なるスローガンの暗記では得られない「腹落ち感」を生み出します。
■ 組織に期待できる効果
パーパス研修を導入した企業では、以下のような効果が期待できます。 1. 離職率の低下社員が自分の働く目的を明確にし、それが企業パーパスと重なることで「この会社で働き続ける理由」が強まります。特に入社3年以内の早期離職防止に効果的です。
2. モチベーションの維持・向上
日々の業務が単なるタスク処理ではなく、「自分の人生の目的に近づくための行動」として再定義されることで、意欲的に取り組む姿勢が育ちます。
3. 主体性の発揮
「会社に言われたからやる」のではなく、「自分がやりたいからやる」という動機に変わることで、自発的な提案や改善行動が増加します。
4. エンゲージメントの向上
「個人の目的」と「企業の目的」が重なる部分を実感できると、社員は組織に強い一体感を持ち、チームとして成果を出そうとする姿勢が高まります。 パーパス研修は、単なる理念浸透を超え、Z世代の社員が「自分の目的」と「会社の存在意義」を重ね合わせるための学びの場です。それは企業にとって、エンゲージメント向上や離職防止といった実利的な効果をもたらすだけでなく、社員一人ひとりのキャリアを豊かにし、組織全体の持続的成長を支える土台となるのです。
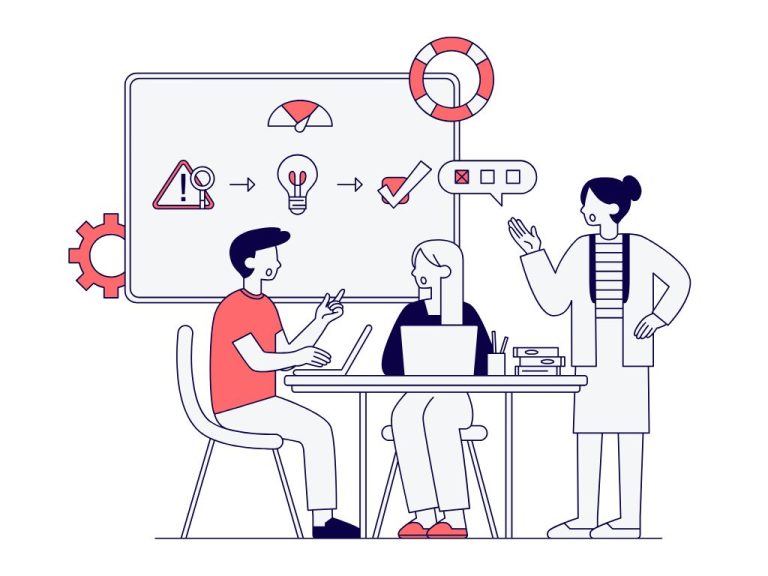
Z世代に刺さるパーパス研修の設計ポイント
パーパス研修の必要性が理解されても、「どのように設計すればZ世代に響くのか?」という問いに直面する担当者は少なくありません。従来の座学型や講義中心の研修では、Z世代の主体性や共感を引き出すことは難しいのが現実です。彼らは「自分で考え、表現し、仲間と対話する」ことを通じて学びを深める特性を持っているため、研修設計においてもその特性を活かす工夫が求められます。ここでは、Z世代に刺さるパーパス研修を設計する際の4つのポイントを紹介します。
1. 自己探求型:自分の価値観を言語化する
Z世代にとって、まず大切なのは「自分自身を知る」ことです。価値観マップやライフラインチャート(人生の重要イベントを振り返る手法)を活用し、自分が大切にしてきた瞬間や意思決定の基準を明確化させます。 例えば、「過去に最も誇りを感じた経験は何か?」「怒りを感じた出来事は何か?」といった問いかけを通じて、自分の根源的な価値観を発見できます。これにより、企業パーパスを理解する前に「自分のパーパス」を言語化する土台が築かれるのです。2. 共感型:企業パーパスを事例やストーリーで理解する
抽象的なスローガンだけでは、Z世代の心には響きません。彼らは「物語」や「リアルな体験」を通じて共感します。そこで、経営層や社員が「なぜこの仕事をしているのか」「どんな場面で会社の存在意義を感じたのか」をストーリーテリングで共有することが効果的です。 例えば、顧客からの感謝の言葉、社会課題解決に寄与したプロジェクトなど、実際のエピソードを交えることで「企業パーパス=現場で実感できるもの」として伝わります。3. 対話型:自分と会社のパーパスの接点を探る
Z世代は一方的に教えられるよりも、対話を通して考えを深める方が得意です。グループワークやワークショップ形式を取り入れ、「自分の価値観と会社のパーパスはどの部分で重なるか?」を議論させることで、理解が深化します。 このプロセスでは、他者の視点に触れることで「自分にはなかった気づき」が得られ、会社とのつながりをより強く感じられるようになります。特に、「個人の目的」と「組織の目的」を対比させながら議論すると、納得感が高まります。4. 実践型:小さなアクションプランを現場で試す
最後に大切なのは、「研修で終わらせない」ことです。自分のパーパスを業務に活かすために、具体的なアクションプランを立てて実践させます。例えば、「来月のプロジェクトで自分の強みを活かす行動を1つ試す」など、小さな挑戦から始めるのがポイントです。 その後、上司やチームと振り返りを行い、成功体験を積み重ねることで、パーパスが「自分の働き方の軸」として根づいていきます。Z世代に響くパーパス研修は、自己探求・共感・対話・実践の4ステップで構築することがカギとなります。単に知識を伝えるのではなく、彼ら自身が「自分の言葉で意味を語れる状態」に導くことが、長期的なエンゲージメントと主体性を育む研修設計の本質なのです。
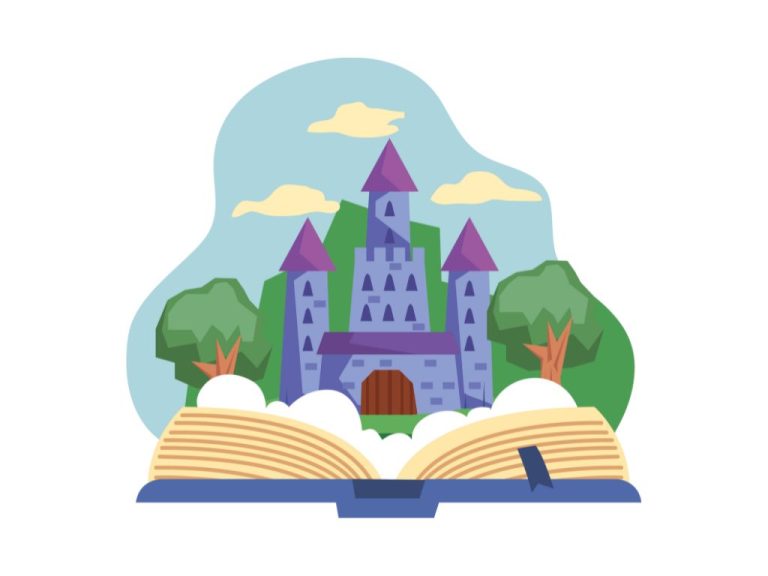
パーパス研修のプログラム例のご紹介
ここまで、Z世代に響くパーパス研修の設計ポイントを整理してきました。しかし「具体的にどのような流れで研修を実施すればよいのか?」という疑問を持つ研修担当者も多いでしょう。そこで本章では、前章で示した自己探求・共感・対話・実践の4ステップをベースにした、実際のプログラム例を紹介します。単なる理念説明にとどまらず、参加者自身が「自分のパーパス」を考え、企業パーパスとつなげ、さらに行動に移せるような構成がポイントです。
1. 導入ワーク:「あなたはなぜ働くのか?」を考える問いかけカード
研修冒頭では、シンプルかつ根源的な問いを投げかけます。例えば「お金以外で仕事から得たいものは?」「もし働く必要がなかったら、あなたは何をしたいか?」といった質問カードを配布し、個人で考えた後にグループで共有します。この段階で参加者は「自分にとっての働く意味」を意識するようになります。2. 自己理解セッション:価値観マップ・ライフイベント振り返り
次に、自分の価値観を掘り下げるワークを行います。 – 価値観マップ:複数の価値観キーワード(例:挑戦・安定・創造・貢献など)を提示し、自分にとって大切な順に並べ替える。– ライフイベント振り返り:これまでの人生で印象に残った出来事を書き出し、それが自分にとって何を意味したのかを考える。 これらのプロセスを通じて、参加者は「自分のパーパスの原型」を言語化できるようになります。
3. 企業パーパス共有:経営層のストーリーテリング
次に、企業のパーパスを一方的に説明するのではなく、経営層や先輩社員が自分の体験を交えて語ります。例えば「顧客から感謝されたエピソード」「社会的意義を感じた瞬間」などをストーリー形式で共有すると、抽象的な言葉が具体的なイメージに変わり、参加者の共感を引き出せます。ここでは「企業パーパス=現場で感じられるもの」という理解を醸成します。4. グループディスカッション:「自分と会社の目的はどう重なるか?」
ここで、自己理解と企業パーパスをつなぐステップに移ります。少人数のグループで「自分の価値観や目的と、会社のパーパスはどこで重なるか?」を議論し、ホワイトボードや模造紙にまとめます。他者の視点を取り入れることで、自分では気づかなかった共通点や新しい解釈に出会えるのが大きな学びになります。5. アクション宣言:自分のパーパスを活かした業務での挑戦
最後に、研修での学びを実践につなげるための「アクション宣言」を行います。各自が「自分のパーパスを活かして、業務でどんな挑戦をするか」をカードや付箋に書き、グループ内で発表します。その後、上司やチームと共有し、定期的に振り返りを行う仕組みを組み込むことで、研修が一過性で終わらず、日常業務に浸透していきます。 このようなプログラム設計によって、参加者は「自分のパーパス」を見出し、それを企業の存在意義と重ね合わせるプロセスを体験できます。結果として「なぜ自分はこの会社で働くのか」という問いに自らの言葉で答えられるようになり、モチベーションとエンゲージメントが高まるのです。
パーパス研修導入の4つのポイント
パーパス研修は、Z世代の価値観に寄り添い、組織全体のエンゲージメントを高める力を持っています。しかし、その効果は「導入の仕方」によって大きく変わります。ここでは、成功のために欠かせない4つの導入ポイントを掘り下げて解説します。
①トップの関与を明確にする
パーパスは企業の存在意義そのものです。そのため、経営層が積極的に関与することが研修の信頼性を大きく左右します。具体的な取り組み例:社長や役員が冒頭で「自分にとっての働く意味」や「なぜこの会社を率いるのか」を語る。単なる理念説明ではなく、自分自身の挫折や学びを交えた“等身大のストーリー”が有効です。
効果:抽象的なスローガンが、経営層の体験を通じて「生きた言葉」になり、社員は「会社が本気でパーパスに向き合っている」と感じるようになります。
効果:抽象的なスローガンが、経営層の体験を通じて「生きた言葉」になり、社員は「会社が本気でパーパスに向き合っている」と感じるようになります。
②双方向性を重視する設計にする
Z世代は「自分の意見を尊重されること」を非常に重視します。そのため、研修は一方通行の講義ではなく、双方向のコミュニケーションを軸に設計する必要があります。工夫のポイント:問いかけカードや付箋を使い、個人の意見を可視化 → グループで共有 → チームごとにまとめを発表、という流れを取り入れる。
事例:ある企業では「自分が誇りを感じた瞬間」を各自で書き出し、それを壁に貼って全員で眺めるワークを実施。その場で自然に対話が生まれ、参加者同士の共感や発見が広がりました。
効果:社員は「聞かされる研修」ではなく「自分もつくり手になる研修」と感じられ、学びの深まりが格段に増します。
事例:ある企業では「自分が誇りを感じた瞬間」を各自で書き出し、それを壁に貼って全員で眺めるワークを実施。その場で自然に対話が生まれ、参加者同士の共感や発見が広がりました。
効果:社員は「聞かされる研修」ではなく「自分もつくり手になる研修」と感じられ、学びの深まりが格段に増します。
③日常業務とつなげる仕組みを用意する
研修が終わった瞬間に効果が消えてしまうのは最大の失敗です。日常業務との接続を仕組みとして組み込むことが、定着のカギとなります。具体例:-アクション宣言を上司と共有し、3か月後に1on1で振り返る。
-チーム会議で「自分のパーパスと業務のつながり」を定期的に発表する。
-人事制度に「パーパスを活かした行動」の評価指標を組み込む。 効果:研修で得た気づきが「やって終わり」ではなく、実際の業務改善やキャリア形成につながり、組織の文化に根づいていきます。
-チーム会議で「自分のパーパスと業務のつながり」を定期的に発表する。
-人事制度に「パーパスを活かした行動」の評価指標を組み込む。 効果:研修で得た気づきが「やって終わり」ではなく、実際の業務改善やキャリア形成につながり、組織の文化に根づいていきます。
④押し付けず、個を尊重する
パーパス研修は「企業の理念を覚えさせる場」ではありません。重要なのは、社員が「自分自身のパーパス」を探り、それと企業パーパスの接点を見つけられることです。工夫のポイント:-「会社の理念に合わせなさい」ではなく、「あなたの価値観とどう重なるかを考えてみよう」と問いかける。
- 経営層や先輩社員のストーリーを参考事例として提示し、「同じでなくても良い」というメッセージを伝える。
事例:ある研修では、社員が「自分のパーパスは家族を支えること」と語ったのに対し、 ファシリテーターが「それも会社の『人を幸せにする』という理念と重なりますね」とフィードバック。本人にとって“個の思いが尊重された実感”が大きなモチベーションにつながりました。
効果:社員は「会社に自分を合わせる」のではなく「自分の価値観を活かせる」と感じ、自然な共感が生まれます。
パーパス研修を成功に導くには、①トップの関与、②双方向性の重視、③日常業務との接続、④個の尊重の4つを押さえることが不可欠です。これらを丁寧に設計・実践することで、社員一人ひとりが「自分のパーパス」を見つけ、それを企業の存在意義と重ね合わせることができます。結果として、Z世代の共感を引き出し、組織全体のエンゲージメントと持続的成長を実現できるのです。
- 経営層や先輩社員のストーリーを参考事例として提示し、「同じでなくても良い」というメッセージを伝える。
事例:ある研修では、社員が「自分のパーパスは家族を支えること」と語ったのに対し、 ファシリテーターが「それも会社の『人を幸せにする』という理念と重なりますね」とフィードバック。本人にとって“個の思いが尊重された実感”が大きなモチベーションにつながりました。
効果:社員は「会社に自分を合わせる」のではなく「自分の価値観を活かせる」と感じ、自然な共感が生まれます。
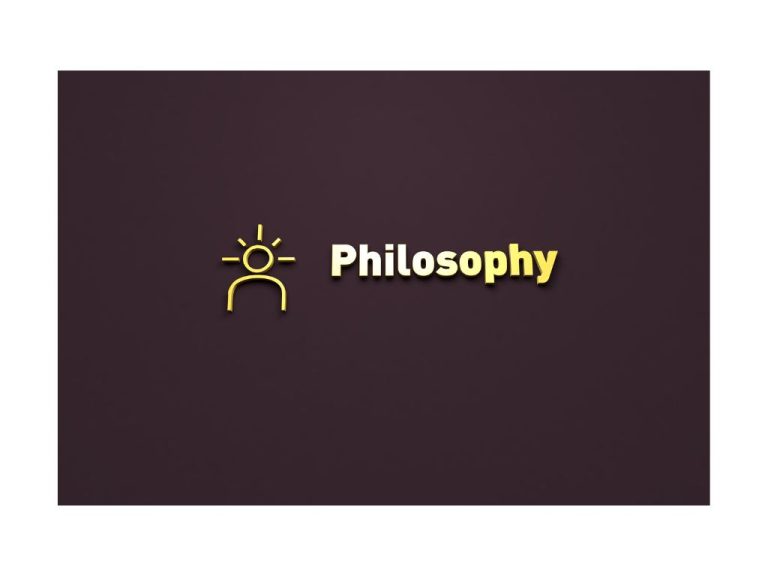
まとめ
Z世代にとって「なぜ働くのか?」という問いは、単なるキャッチフレーズではなく、自分の人生やキャリアを形づくる根幹となるテーマです。彼らはデジタルネイティブとして多様な価値観に触れて育ち、「意味のある仕事」「社会に貢献できる仕事」を強く求めています。そのため、企業がパーパスを一方的に伝えるだけでは共感は得られません。 パーパス研修は、社員自身が自己探求を通じて「自分のパーパス」を言語化し、企業の存在意義と結びつけて考える場を提供します。その結果、社員は「自分はこの会社でなぜ働くのか?」を自らの言葉で語れるようになり、仕事への納得感や主体性が高まります。さらに、研修を評価制度や1on1などの仕組みと接続することで、エンゲージメントの向上や離職防止といった具体的な成果にもつながります。 つまり、パーパス研修はZ世代へのアプローチに留まらず、組織全体の持続的な成長を支える重要な投資です。個人の目的と企業の目的が重なり合うとき、社員は自らの力を最大限に発揮し、企業もまた社会により大きな価値を提供できるようになるのです。
【執筆者情報】
ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃
研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。