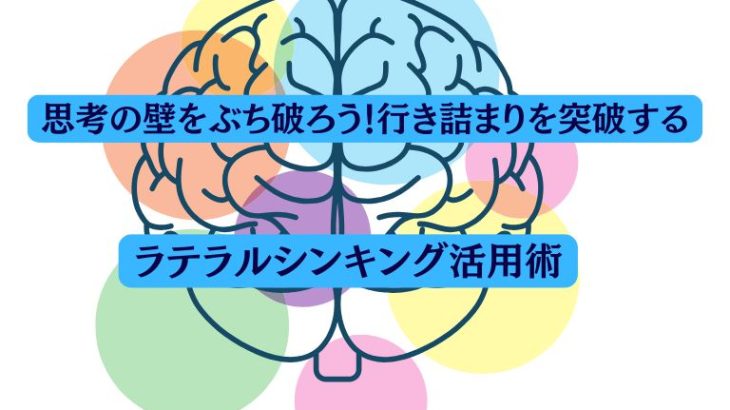・同じ問題を何度も話し合っているのに、結局は従来のやり方に落ち着いてしまう
・他社が革新的なサービスを打ち出しているのを横目に、自社は動けずにいる 現代のビジネス環境は、これまで以上に変化が激しく、予測が難しい時代です。テクノロジーの進化、消費者ニーズの多様化、競合の参入スピードは年々加速しています。かつては「過去の成功事例」や「業界の常識」に従えば安定的に成果を上げられました。しかし今や、過去のパターンに沿った判断では通用しない場面が増えています。 たとえば、ある老舗百貨店では長年「来店して商品を購入する」という購買モデルを前提に運営を続けていました。しかしコロナ禍で来店者数が激減し、従来の施策では売上が回復しない状況に陥りました。その時、若手チームが提案したのは「店内スタッフがライブ配信で商品を紹介し、その場でオンライン購入できる仕組み」でした。結果、新規顧客層を獲得し、売上は回復基調へ。これはまさに、従来の発想の枠を超えたラテラルシンキングが生んだ成果です。 このように、行き詰まりの打破には“常識の外側”から発想する力が欠かせません。そして、その力を体系的に鍛える方法こそが「ラテラルシンキング」です。本コラムでは、なぜラテラルシンキングが今必要なのか、どのように使えば現場で成果につながるのかを、具体事例や実践法とともに解説していきます。

ラテラルシンキングとは?
ラテラルシンキング(Lateral Thinking)は、日本語では「水平思考」と呼ばれます。 1967年、マルタ出身の心理学者エドワード・デ・ボノが提唱した概念で、従来の「垂直思考(ロジカルシンキング)」に対する新しい発想法として知られています。 垂直思考が、1つの方向に向かって深く掘り下げていく「井戸掘り型」の思考法だとすると、ラテラルシンキングは、横方向に視点を広げて新しい井戸を探す「探索型」の思考法です。 つまり、垂直思考は既知の情報をもとに「正しい答え」に到達するための道筋を組み立てますが、ラテラルシンキングは「そもそも正しい答えは1つではない」という前提で、多様な解決策を見つけ出そうとします。
1. ロジカルシンキングとの違い
まずは、この2つの思考法の違いを整理してみましょう。| 項目 | 垂直思考(ロジカルシンキング) | 水平思考(ラテラルシンキング) |
| アプローチ | 原因を分析し、筋道を立てて結論を導く | 前提を疑い、視点を変えて発想する |
| ゴール | 正確性・妥当性の高い答え | 新規性・独創性のある答え |
| 適用場面 | 既知の問題・答えが存在する課題 | 未知の問題・答えがない課題 |
| メリット | 再現性が高い、信頼されやすい | 斬新なアイデアを生みやすい |
| デメリット | 新しい発想は出にくい | 実行性のない案が出る可能性 |
実行性のない案が出る可能性
例えば、売上が落ちている店舗の改善策を考える場面で、垂直思考では「原因分析→改善策の順番で検討」という流れになります。 「客数減少」が原因なら、「集客イベントを増やす」「広告費を増やす」といった従来型の施策が出てくるでしょう。 一方、ラテラルシンキングでは「そもそも店舗で販売する必要があるのか?」という前提を疑う発想から、「オンラインショップ化」や「店舗をコミュニティスペース化する」など、これまでとは全く異なる方向性のアイデアが出てくる可能性があります。2. ラテラルシンキングが必要とされる背景
現代のビジネスは、以下のような特徴を持っています。 ✓ 正解が存在しない課題が増えている(例:新市場開拓、働き方改革)✓ 過去の成功パターンが通用しない(例:コロナ禍による消費行動の変化)
✓ 競合や異業種からの新規参入が早い(例:IT企業が金融・医療分野に進出) こうした環境では、従来の延長線上の発想だけでは突破口を見つけるのが難しくなります。むしろ、「全く異なるアプローチ」こそが差別化や生き残りの鍵になります。ラテラルシンキングは、まさにこの“異なるアプローチ”を意図的に生み出すための技術です。
3. ビジネスでの活用シーン
ラテラルシンキングは、多くの業務領域で活用できます。 ● 新規事業開発例:飲食業界で「店舗提供」が常識だったところを、ゴーストキッチン(厨房のみ)モデルに転換し、新たな顧客層を獲得。
● 商品企画
例:カメラメーカーが「高画質写真を撮る」機能だけでなく、「映像をライブ配信する」機能を追加し、YouTuber市場を開拓。
● 業務改善
例:会議の効率化を目的に「時間短縮策」を探すのではなく、「そもそも会議をしない」方針を採用し、文書ベースの合意形成に変更。
4. ラテラルシンキングを阻む壁
多くの組織でラテラルシンキングが根付かない理由は、固定観念と心理的ハードルです。 ● 固定観念:「それはうちの業界では無理」「過去にやったけどうまくいかなかった」● 失敗への恐怖:「変わったことを提案して否定されたらどうしよう」
● 評価制度の問題:新しい発想よりも、リスクの少ない改善策が評価される文化 これらを打破するには、まず「前提を疑う」ことに慣れる必要があります。そのためには、日常業務でラテラルシンキングを試し、経験値を積むことが大切です。 ラテラルシンキングは、単なる“ひらめき”ではなく、意図的に発想の枠を外すための技術です。垂直思考と併用することで、より実行性の高い斬新な解決策を生み出せます。次章では、なぜ行き詰まりが発生するのか、その原因とラテラルシンキングによる突破方法について掘り下げていきます。
行き詰まりの原因は“思考の固定化”にある
ビジネスや日常業務で「打つ手がない」「何をやっても変わらない」と感じる瞬間があります。多くの場合、その行き詰まりの正体は**「アイデアが枯渇した」ことではなく、思考の方向が固定されてしまっていること**にあります。つまり、私たちは無意識のうちに「こうあるべき」という見えないレールの上を走ってしまっているのです。
1. 固定観念が発想を縛る
固定観念とは、長年の経験や業界の慣習、過去の成功事例から形成された“暗黙のルール”です。便利な反面、このルールが発想の幅を狭める原因になります。 事例①:旅行業界の宿泊前提モデルかつて旅行業界では、「旅行=宿泊を伴うもの」という前提が当たり前でした。そのため、企画も宿泊プランを中心に組まれていました。しかし、短時間での気分転換や非日常体験を求める顧客層に対しては訴求力が弱く、日帰り旅行市場の拡大というチャンスを逃してしまっていたのです。 事例②:出版業界の紙依存
長らく「本=紙媒体」が常識だった出版業界も、電子書籍市場への参入が遅れたことでAmazon Kindleなどの外部勢力に市場を奪われました。紙の価値を信じるあまり、消費者の利便性という新しい軸を見落としていた典型例です。
2.「業界の常識」という見えない壁
固定観念は個人だけでなく、業界全体の文化として存在します。これを「業界の常識」という見えない壁と呼びます。この壁は強力で、次のような形で表れます。 ✓ 過去の成功体験に依存:「この方法でうまくいったから今回も大丈夫」✓ 他社と足並みを揃える圧力:「業界全体でやっていないことはリスクが高い」
✓ 新規アイデアへの懐疑:「前例がない=危険」 この壁を壊すには、「その常識は本当に必要か?」という問いを繰り返すことが重要です。
3. 心理的要因も大きい
思考が固定される原因は、文化や慣習だけではありません。人間の心理的な性質も大きく影響します。 コンフォートゾーンの安心感人は慣れたやり方に安心を感じます。未知のアプローチは不安を伴うため、避けたくなる傾向があります。
損失回避バイアス
「新しいことを試して失敗するより、現状維持で安全に過ごしたい」という心理が働きます。これは経済学や行動科学でも確認されている現象です。
評価制度の影響
多くの組織では、成果よりもリスク管理や安定運営が評価されがちです。そのため、革新的な提案は「無謀」と見なされ、提案者が損をする可能性が高くなります。
4. 行き詰まりは「課題そのもの」ではなく「思考の枠」にある
重要なのは、「行き詰まりは課題そのものの難しさではなく、課題の見方が限定されていることによって生まれる」という視点です。 例えば、「売上を上げる」という課題があった場合、多くの人は「販促を強化する」「広告予算を増やす」という方向でしか考えません。しかし、ラテラルシンキングでは「そもそも売上とは何か?」という根本的な定義を疑い、「収益モデルそのものを変える」という選択肢にたどり着くことがあります。5. 思考の固定化を打破する第一歩
思考の固定化を外すためには、次のような習慣を取り入れることが有効です。 ➀「逆の質問」をしてみる例:「どうすれば成功するか?」ではなく「どうすれば失敗するか?」と考える。 ➁ 他業界の事例に触れる
異なる業界の課題解決方法を自分の業務に応用できないかを探る。 ➂ 仮想制約を設ける
「予算ゼロでこの課題を解決するには?」など、条件をあえて極端に設定して考える。 ➃ 定期的に前提を洗い出す
「なぜこのやり方なのか?」をチームで問い直す時間を設ける。 行き詰まりは、多くの場合「アイデアがない」ことではなく、「思考が同じ場所をぐるぐる回っている」ことによって生じます。 その固定化された思考の枠を壊すことができれば、課題は全く新しい姿を見せ始めます。次章では、ラテラルシンキングを使ってその壁を壊すための具体的な技法を紹介していきます。

ラテラルシンキングで壁を壊す5つの技法
思考の固定化を外し、行き詰まりを突破するためには、「常識の外側」に意図的に踏み出す技術が必要です。ラテラルシンキングにはさまざまな手法がありますが、ここではビジネス現場で使いやすく、かつ成果につながりやすい5つの技法を紹介します。
1. 逆転発想法(Reversal Thinking)
【考え方】通常は「どうすればうまくいくか?」と正の方向から考えますが、逆転発想法ではあえて「どうすれば失敗するか?」を考え、そこから逆算して改善策を導きます。 例
・イベント集客
「どうすれば集客できるか?」ではなく、「どうすれば集客できないか?」を考える。
→「告知しない」「アクセスの悪い会場にする」などの失敗要因を列挙し、それを防ぐ施策を練る。
・顧客満足度向上
「どうすれば顧客が不満を持つか?」を洗い出し、それを避ける形でサービス改善を行う。 【ポイント】
-ネガティブ発想は制約を外すきっかけになる
-会議で行うと笑いも生まれ、発言が活発になりやすい
2. 制約の破壊(Challenging Assumptions)
【考え方】「それは当然の条件」という前提をあえて外してみることで、新しい可能性を探ります。 例
-飲食店の常識を壊す
「飲食店は店員が接客する」という前提を外し、セルフオーダー・セルフ配膳のシステムを導入。人件費削減と回転率向上を同時に達成。
-会議運営の常識を壊す
「会議は全員で集まる」という前提を外し、チャット上で非同期進行する「会議ゼロ化」に成功した企業もある。 【ポイント】
-「なぜこの条件が必要なのか?」を問い直す
-他業界の事例を参考にすると発想が広がる
3. ランダム刺激法(Random Entry Technique)
【考え方】課題と全く関係のない単語や画像をきっかけに連想を広げ、偶然の組み合わせから新しい発想を生み出します。 例
– 商品企画会議で、辞書からランダムに選んだ単語「海」をヒントに、オフィスチェアの新色として「マリンブルー」を採用。結果、若年層の購買が増加。
– 社内研修テーマを「旅行」という無関係なキーワードから発想し、「社員スキル探検ツアー」という参加型研修プログラムを企画。 【ポイント】
– 偶然性を活用すると、思考が意外な方向へジャンプする
– 付箋やカードゲーム形式にすると参加者の発想が出やすい
4. 組み合わせ発想(Concept Combination)
【考え方】異なる要素や業界の手法を掛け合わせ、新しい価値を創出します。 例
-フィットネス × カフェ
トレーニング後に健康的なスムージーを提供するジムカフェ。健康志向の顧客層を獲得。
-ホテル × コワーキング
宿泊と仕事スペースを融合し、ワーケーション需要を開拓。 【ポイント】
-「異質なもの同士」を組み合わせるほど斬新なアイデアが生まれやすい
-他業界の成功事例を観察することが発想の種になる
5. SCAMPER(スキャンパー)法
SCAMPER法は、広告業界や新商品開発などで広く使われる発想ツールで、アメリカの広告マン アレックス・オズボーンの発想法をもとに、ボブ・エバールが7つの視点として体系化したものです。既存のアイデアや製品を7つの切り口で見直すことで、新しい発想を生み出すのが特徴です。 SCAMPERの7つの視点S(Substitute)置き換える
→ 材料・工程・人・場所などを別のものに置き換える
例:紙のチケットをQRコードに置き換える C(Combine)組み合わせる
→ 異なる要素を掛け合わせる
例:カフェと書店を組み合わせたブックカフェ A(Adapt)応用する
→ 他分野の技術や方法を応用する
例:工場の自動搬送システムを病院の薬品搬送に応用 M(Modify / Magnify)修正・拡大する
→ デザイン・機能・サイズ・色を変える、強調する
例:スマホの画面を大型化し、動画視聴に特化 P(Put to other uses)他用途に使う
→ 本来の目的以外で使う
例:ワイン木箱を収納家具として販売 E(Eliminate)削除する
→ 機能・工程・要素を削る
例:ホテルのフロント業務を無人化 R(Reverse / Rearrange)逆転・再配置する
→ 順序や役割を逆にする
例:先に代金を支払い、その後自由に商品を選ぶレストラン方式 SCAMPERは、ラテラルシンキングの「発想を横に広げる」部分を体系的に進めるツールです。 特に、アイデアが出尽くしたように見える段階でSCAMPERの7つの質問を投げかけると、固定観念の枠を外すきっかけになります。
実務導入のコツ
これら5つの技法は、単発で使うだけではなく、組み合わせることで効果が倍増します。たとえば、「制約の破壊」で前提を外したあと、「組み合わせ発想」で異業種のアイデアを加えると、実行可能性の高い案が出やすくなります。 また、これらの手法は会議の冒頭や企画段階で使うのが効果的です。ロジカルシンキングで検証する前に、幅広い選択肢を出すステップとして導入すると、発想のバリエーションが一気に広がります。 ラテラルシンキングは「ひらめき待ち」ではなく、意図的に思考の枠を壊すための方法論です。逆転発想、制約の破壊、ランダム刺激、組み合わせ発想という4つの技法は、いずれも現場で即使える実践ツールです。次章では、これらの技法が実際にビジネス現場で成果を生んだ具体事例を紹介していきます。
研修で身につけるラテラルシンキング
ラテラルシンキングは本や記事で学ぶこともできますが、真の効果を得るためには「体験を通じた学習」が欠かせません。なぜなら、発想の枠を外すには、理論の理解だけでなく「自分の思考のクセに気づく体験」が必要だからです。ここでは、企業研修としてラテラルシンキングを導入する際の進め方と設計ポイントを解説します。
1. 研修の狙いを明確にする
ラテラルシンキング研修の目的は大きく3つに分けられます。 1. 固定観念を外すマインドセットを養う常識や慣習に縛られない思考態度を身につける。
2. 具体的な発想技法を習得する
逆転発想法や制約の破壊などのツールを使いこなせるようにする。
3. 業務課題に応用できる力をつける
実際の自社課題に当てはめて解決策を生み出す。 研修前に目的を明確化することで、内容のカスタマイズがしやすくなります。
2. 講義+ワーク型の二段構成が効果的
座学だけでは「分かったつもり」で終わってしまうため、講義と演習を組み合わせた構成が有効です。 講義パート(インプット)・ラテラルシンキングの定義、垂直思考との違い
・代表的な技法(逆転発想、制約破壊、ランダム刺激、組み合わせ発想)の説明
・成功事例と失敗事例の比較 ワークパート(アウトプット)
・グループでお題をもとに発想ゲーム(例:「予算ゼロで売上を倍増させる方法」)
・制約条件を変えた複数ラウンドでアイデア出し
・最終的に現実的な施策に落とし込む
3. ゲーム形式で体験させる
ラテラルシンキングは、実際に「常識を壊す体験」をしないと本当の意味で理解できません。そのため、カードゲームやシナリオゲーム形式が効果的です。 例1:前提崩しゲームお題:「レストランの売上を伸ばせ」
1ターン目:普通に案を出す
2ターン目:「店員なし」という制約を加える
3ターン目:「料理提供なし」という極端な条件を加える
出てきたアイデアから、実現可能性を検証 例2:ランダム刺激ワーク
ランダムに配られた単語カード(例:「海」「時計」「子供」)を使い、お題に沿った発想を生み出す
4. 自社課題への応用演習
研修で出したアイデアが自社の実務に活かせなければ意味がありません。最後に必ず**「自社課題に即したアイデア創出セッション」**を行います。 進め方は以下の通りです。 1. チームごとに自社の課題を1つ選定2. ラテラルシンキング技法を使って10案以上の解決策を出す
3. 最も実行可能性の高い案を選び、簡易アクションプランを作成
4. 全体発表で共有し、相互フィードバックを行う
5. フォローアップで定着を図る
研修後に現場で活用し続けるためには、フォローアップ施策が重要です。 – 月1回の「発想会議デー」を設定– 社内掲示板やチャットで「前提崩しアイデア」を投稿する場をつくる
– 成果事例を社内で共有し、成功体験を広める
6. 成功する研修設計のポイント
批判禁止ルール:発想段階では否定せず、とにかく数を出す
時間制限の活用:短時間でアイデアを出すことで脳が活性化
異質なメンバー構成:異なる部署・年代を混ぜると発想が広がる
現場直結テーマ:参加者が「これは自分の仕事に関係ある」と感じる題材を扱う
ラテラルシンキング研修は、単なる「アイデア発想の練習」ではなく、組織文化や業務プロセスの変革にもつながります。講義で理論を理解し、ワークで体験し、自社課題に応用し、さらにフォローアップで定着させる。この一連の流れを設計することで、研修の効果は飛躍的に高まります。
時間制限の活用:短時間でアイデアを出すことで脳が活性化
異質なメンバー構成:異なる部署・年代を混ぜると発想が広がる
現場直結テーマ:参加者が「これは自分の仕事に関係ある」と感じる題材を扱う
まとめ
本コラムでは、ラテラルシンキングという思考法が、ビジネスの行き詰まりを打破し、常識の外から新しい解決策を生み出すための強力な武器であることを見てきました。 現代のビジネス環境は、過去の成功パターンや業界の常識が通用しにくい時代です。市場の変化は速く、顧客ニーズは多様化し、競合は異業種からもやってきます。そんな中で「正しい答えを導く」だけの垂直思考だけでは、突破口を見つけるのが難しくなります。 ラテラルシンキングの本質は「答えの範囲を広げること」にあります。前提条件を疑い、視点をずらし、異質な要素を掛け合わせることで、これまで見えなかった選択肢が浮かび上がります。それは時に奇抜に見えるかもしれませんが、実際には多くのイノベーションやヒット商品の裏側に、この発想法が隠れています。 ラテラルシンキングは特別な才能ではなく、誰でも身につけられるスキルです。しかし、そのためには「常識を疑う勇気」と「多様な発想を受け入れる環境」が必要です。 最初は奇抜に感じるアイデアも、組織で検証すれば実行可能な戦略へと育ちます。大切なのは、発想を出す段階で否定せず、幅を広げること。そして、試行錯誤の中から実行に移せるものを見つけていくことです。 行き詰まりは終わりではありません。それは、これまでの思考の枠を壊し、新しい視点を得るチャンスです。ラテラルシンキングは、そのチャンスを確実に成果へと変えるための道具です。 壁の外には、まだ見ぬ選択肢が無限に広がっています。その一歩を踏み出すかどうかで、あなたや組織の未来は大きく変わります。今日からでも、まずは1つの固定観念を疑うことから始めてみてください。
【執筆者情報】
ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃
研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。