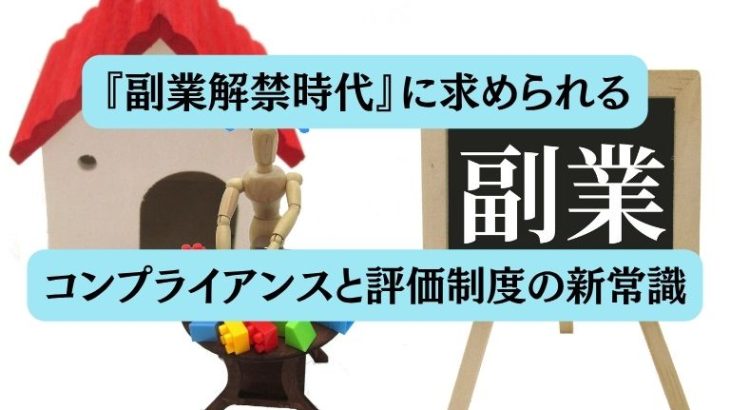✓「競合他社で働かれたらどうするのか」
✓「社員が副業で得たスキルや利益を、評価にどう反映すればいいのか」 このような懸念や疑問は、実務において極めて現実的な課題です。特に、コンプライアンス(法令順守)や就業規則の整備、また評価制度との整合性といった点は、多くの企業で議論が分かれる部分です。 副業を「自由に認める」だけでは、企業としてのリスクが増大します。一方で、過度な制限を設けてしまえば、優秀な人材の流出や、社員のモチベーション低下につながりかねません。つまり、いま企業に求められているのは、「副業を認めるかどうか」ではなく、「どのようにルールと仕組みを整え、社員の多様な働き方と調和させていくか」という視点です。 本コラムでは、副業解禁時代の背景を踏まえた上で、企業が直面するコンプライアンスリスクとその対策、そして変化する時代に対応した人事評価制度のあり方について具体的に解説していきます。制度の形だけでなく、社員と組織が互いに信頼し合える関係を築くための「新しい常識」とは何か。副業を「リスク」として管理するのではなく、「資産」として活用するためのヒントをお届けします。

なぜ今「副業解禁」が注目されるのか?
副業解禁はもはや一部の先進企業だけの話ではない
「副業解禁」というキーワードを耳にする機会が増えました。かつてはごく一部の先進的なIT企業やスタートアップの文化のように見られていた副業推奨の動きが、今では大企業から地方中小企業にまで広がりつつあります。背景には、日本社会を取り巻く雇用環境・経済環境の大きな変化があります。 従来の日本型雇用システム、すなわち「終身雇用」「年功序列」「企業内教育」は、長らく社員と企業の双方にとって安定と安心をもたらすものでした。しかし、グローバル化・少子高齢化・技術革新によって、企業の寿命やビジネスモデルが急激に変わる現代において、その仕組みはもはや持続可能ではなくなってきています。 このような背景の中、政府は2018年に「モデル就業規則」から「副業・兼業の原則禁止」という文言を削除し、副業推進を明確に後押ししました。働き方改革実行計画でも副業は重点施策のひとつに位置づけられており、「柔軟な働き方」「キャリア自律」「生涯現役」の観点から、その社会的意義が注目されています。Z世代・ミレニアル世代の価値観変化
副業解禁の流れをさらに加速させているのが、若い世代の働き方に対する価値観の変化です。Z世代(1990年代後半〜2000年代生まれ)やミレニアル世代(1980〜1995年頃生まれ)の多くは、単に「会社に勤めて収入を得る」ことを目的とはしていません。 彼らは「自分らしく働きたい」「社会に貢献したい」「複数の分野にチャレンジしたい」といった多様な志向を持っており、会社だけにキャリアを依存しない“分散型の生き方”を重視しています。YouTubeやSNS、オンラインマーケットプレイスの発展もあり、スキルや知識を活かして個人で収益を上げる手段が増えた今、副業は“特別なもの”ではなく、自然な選択肢となっています。 また、「一社では得られない経験」や「本業に還元できる知見」を副業から得ようとする社員も多く、副業が「キャリア形成の一環」として捉えられている傾向が強まっています。副業がもたらす企業へのメリット
企業にとって副業は、単なる社員の自己実現支援ではありません。視点を変えれば、実は大きなメリットも内包しています。 たとえば、副業を通じて社員が獲得した外部スキルや経験は、本業にも波及効果をもたらします。副業でマーケティングやデザインのスキルを磨いた社員が、自社製品の販促にも貢献するケースは少なくありません。また、地域のNPOやベンチャー企業で活動することにより、社会課題への感度が高まり、企業のSDGs活動や新規事業創出に生かされたという事例も増えています。 さらに、社員が副業で得た“外の視点”を組織内に持ち込むことで、閉鎖的になりがちな企業文化に新しい風が吹き込まれるという副次効果も期待されます。一方で拭えない企業側のリスクと懸念
もちろん、メリットがある一方で、企業が副業解禁に慎重になるのも理解できます。主な懸念は以下のようなものです。 業務への支障:副業に時間やエネルギーを取られ、本業のパフォーマンスが低下するのではないか。情報漏洩リスク:他社での業務を通じて、自社のノウハウや顧客情報が漏れる危険性。
競業避止違反:同業他社や競合に近い事業で副業をされた場合の損失。
労働時間の管理:法的には複数の事業所での労働時間も通算して管理する必要があるが、実務は煩雑。
評価制度との不整合:副業の実績や学びを、どこまで本業の評価に加味するべきか。 これらの懸念に対処するためには、就業規則の整備、申請・許可制度の導入、評価制度の見直しなど、組織としての「受け皿づくり」が不可欠です。
これからの企業に求められる姿勢とは
副業を「推奨すべきか/禁止すべきか」の二択で語る時代は終わりつつあります。これからの時代に求められるのは、「社員の副業活動を、組織としてどのように整えて共存していくか」という“共創”の視点です。 副業を認めることで得られるのは、社員のやる気や能力向上だけではありません。柔軟な制度と透明性のあるルールを通じて、社員との信頼関係を強化し、魅力ある職場として人材の定着・採用競争力も高めていくことが可能です。副業におけるコンプライアンスリスクとは
「副業=自由」と誤解されがちな落とし穴
副業を認める企業が増える一方で、「副業は自由にやってよいもの」「会社は干渉すべきでない」といった誤解が社員側にも見られるようになってきました。しかし、副業は本業とは異なる環境での労働や取引を伴う以上、法的・倫理的なリスクが生じるのは避けられません。 企業が副業を容認する際に最も注意すべきは、“社員個人の自由”と“企業としてのリスク管理”のバランスです。副業にまつわるトラブルは、一歩間違えば企業全体の信頼失墜や損失につながる可能性があるため、事前の予防とルール整備が不可欠です。 ________________________________________
■ よくある副業トラブルとリスク事例
以下に、副業に関して実際に起きやすいトラブルと、その背景にあるコンプライアンスリスクを具体的に紹介します。 1. 情報漏洩リスク
たとえば、営業職の社員が副業でマーケティングコンサルタントとして他社を支援していた場合、自社の顧客情報やノウハウが意図せず流出する危険があります。本人にそのつもりがなくても、類似業界や競合に関わる副業は、機密保持義務の観点から非常にセンシティブです。 2. 競業避止義務の違反
副業が同業種や競合サービスに関わる場合、たとえ個人事業であっても「競業避止義務違反」に該当する可能性があります。特に、退職後ではなく“在職中”に競合事業に関与することは、企業の信用や利益を著しく損なうおそれがあるため、明確な禁止ルールが必要です。 3. 長時間労働と健康管理
副業によって総労働時間が増加し、過労や健康障害につながるリスクも見逃せません。労働基準法では「複数の使用者に雇われた場合の労働時間は通算する」と定められており、仮にA社で8時間勤務した社員が、副業でさらに5時間働けば、13時間労働となり労基法違反になる可能性があります。 4. 職場の秩序の乱れ
副業が「本業への意欲低下」や「チームとの温度差」を生み、職場の一体感を損なう場合があります。「あの人は副業で稼いでるから本業に手を抜いてる」といった同僚間の不信や軋轢が生まれた場合、パフォーマンス以前に職場環境そのものに悪影響を及ぼすこともあります。 5. 副業の内容が公序良俗に反するケース
ギャンブル性の高い投資案件や、風俗関連、マルチ商法的な業務など、企業の倫理観や社会的信頼を損なうような副業に従事するケースも報告されています。社員の私生活とはいえ、会社の看板を背負った存在である以上、放置はできません。
________________________________________

リスク対策の第一歩は「就業規則の明文化」
こうしたリスクを未然に防ぐためには、まず就業規則や社内ガイドラインを明文化することが重要です。以下のようなポイントを盛り込むことで、社員にとっても企業にとっても「何がOKで、何がNGか」を明確にすることができます。
就業規則に含めるべき内容の例
•副業の定義(どこまでが副業に該当するか)•副業申請の手続き(許可制か届出制か)
•副業の禁止事項(競合・守秘義務・公序良俗など)
•労働時間の申告ルール
•会社名の使用禁止に関する項目
•トラブル時の対応(会社としての関与範囲) なお、就業規則に「副業を禁止」と一律に定めることは、現在の社会的流れや法的観点からもリスクがあります。たとえば、社員が副業禁止規定を理由に訴訟を起こす可能性もあり、「一律禁止」ではなく「一定の条件下で制限または許可」という柔軟な設計が推奨されます。
許可制 or 届出制?どちらが良いのか
副業を制度として整える際、企業が悩むのが「許可制」にするか「届出制」にするかという点です。それぞれにメリット・デメリットがあるため、企業の文化や規模、業種に応じた選択が必要です。
| 区分 | 許可制 | 届出制 |
| 特徴 | 上司・人事部門の許可を得て初めて副業可 | 社員が報告すれば原則可 |
| メリット | リスクを事前に把握しやすい | 柔軟な運用ができる/社員の心理的ハードルが低い |
| デメリット | 手続きが煩雑・申請が抑制されやすい | リスク把握が後手に回る可能性 |
社員と企業の“信頼関係”が何よりのコンプライアンス対策
制度やルールを整えることはもちろん重要ですが、実際に副業が問題に発展するかどうかは、“社員と企業との信頼関係”にかかっていると言っても過言ではありません。 社員が「正直に相談できる空気」が職場にあるかどうか。企業が社員の成長や挑戦を“応援する姿勢”を持っているかどうか。そうした文化の有無が、副業にまつわるリスクを大きく左右します。 形式的な規則だけでは、複雑化する働き方の実態に対応しきれません。だからこそ、ルールとあわせて「相談しやすさ」「透明性」「納得感」といった、ソフト面の整備も重視する必要があります。
評価制度はどう変わるべきか?
副業が常態化する時代に問われる“評価の前提”
かつての日本企業における評価制度は、「会社への忠誠心」や「在籍年数」「上司からの印象」によって成り立っていました。社員はフルタイムで自社の仕事に従事し、評価はその貢献度のみによって測られる――この前提が長らく揺らぐことはありませんでした。 しかし、副業が当たり前となり、社員が「社外での活動」にも時間と労力を投じるようになった今、その前提が崩れ始めています。 「副業で成功した社員は、本業を疎かにしているのでは?」 「副業で得た知見が本業に役立っている場合、それをどう評価するべきか?」 「副業をしていない社員との評価の公平性は保たれるのか?」 このような疑問が人事担当者やマネジメント層の中で浮上しており、従来型の評価制度では対応しきれないケースが増えています。副業の拡大は、単なる「制度対応」だけでなく、「評価軸の再設計」という企業文化の根幹を揺さぶるテーマでもあるのです。副業の成果は評価すべきか?
まず議論になるのは、「副業での成果を評価に含めるべきかどうか」という点です。 たとえば、ある社員が週末にフリーランスとしてITスキルを磨き、業界での実績や賞を得たとします。この経験が本業の業務効率化やプロジェクト成功に貢献しているとしたら、会社としてもその価値を認めたいところでしょう。 しかし一方で、「社外の成果」を評価対象に入れてしまうと、次のような懸念が生じます。 •社外活動を推奨しすぎることで、本業に集中しない人が増えるのでは?•副業ができる人(スキルや時間のある人)ばかりが評価され、不公平になるのでは?
•評価基準が曖昧になり、主観的な判断が増えてしまうのでは? こうした懸念から、多くの企業では「副業そのものの成果」ではなく、「本業への影響」や「スキルの還元度合い」にフォーカスして評価を行う方針を採っています。
“副業の成果”ではなく“本業への貢献”に着目せよ
現実的かつ公平な評価のためには、「副業の内容」ではなく、「その経験が本業にどう生かされたか」に注目する姿勢が求められます。たとえば、以下のような視点です.| 副業経験 | 本業への貢献評価の例 |
| Webデザインの副業 | 社内資料の品質向上、顧客提案資料の改善 |
| スポーツコーチの副業 | チームマネジメント能力の向上、部下育成の手法導入 |
| 副業で得たスキルを活かした勉強会開催 | 社内ナレッジ共有、他社員への良い刺激 |
評価制度に必要な3つの視点
副業時代にふさわしい評価制度を設計するためには、以下の3つの視点が重要です。 ①【成果の可視化】副業の有無にかかわらず、「どんな成果を出したか」「どのような貢献をしたか」を具体的に可視化し、評価者間で共通認識を持つ仕組みが求められます。主観や印象ではなく、事実ベースでフィードバックできる体制づくりがカギとなります。 ②【行動プロセスの評価】
成果だけでなく、行動プロセスや取り組み姿勢、チームへの影響などを評価する仕組みも整備しましょう。副業によって得た学びや挑戦が、行動変容や意識改革につながっていれば、それは立派な成長の証といえます。 ③【社員の目的意識と連動】
副業も本業も「キャリア形成の手段」として位置づけることで、評価軸を“成果”だけでなく、“成長の方向性”にまで拡張することができます。1on1やキャリア面談の中で、副業に関する意図や目的をすり合わせ、社員がどう成長したいのかを確認する場を設けることも効果的です。 最後に強調したいのは、「副業を評価するかどうか」は制度だけで決まる問題ではない、ということです。評価の納得性や公平性は、制度設計以上に、日々のマネジメントやコミュニケーションのあり方にかかっています。 評価者である上司が部下の副業に関心を持ち、成長を支援する姿勢を持てるかどうか。社員が自らのキャリアと向き合い、本業への貢献を言語化できるようになるかどうか。そのためには、評価の場を単なる「査定」から「対話」へと進化させる必要があります。

ルールづくりと風土づくり、両輪で整備を
ルールを整備するだけでは副業はうまくいかない
副業を認めるかどうか――この問いに対し、「許可制」や「届出制」といった制度設計を行う企業は増えています。しかし、制度の整備だけで安心していては、思わぬトラブルや誤解を招きかねません。むしろ制度があることで、「ルールさえ守っていれば会社に相談しなくても良い」と誤認されることすらあるのです。 副業時代において求められるのは、「ルール(制度)」と「風土(文化)」を両輪として整備することです。社員が納得し、企業も安心して副業を受け入れられるためには、“制度の明文化”と“対話の文化”の両方が不可欠なのです。 ________________________________________
■ 副業ガイドライン:ルール整備の要
制度面での整備は、まずは副業ガイドラインの策定から始めるのが現実的です。以下は、企業が整備すべき代表的なルールとガイドラインの要素です。 🔹 副業ガイドラインに含めるべき要素
| 項目 | 内容例 |
| 副業の定義 | 収入の有無を問わず、本業以外での継続的な活動を含む |
| 対象範囲 | 週末・夜間だけでなく、年次休暇中の活動も含める場合あり |
| 届出/許可のルール | 届出制か許可制か、何日前までに申請すべきか |
| 禁止事項 | 競業行為、信用毀損行為、情報漏洩、公序良俗違反など |
| 労働時間管理 | 労基法に基づく通算管理と、健康管理に関する取り決め |
| トラブル対応 | 副業先での問題発生時に企業が関与するか否かの方針 |
「相談できる空気」をどう作るか? 風土づくりのカギ
副業に関する社内ルールが整っていても、社員がそれを「活用しやすい」と感じていなければ機能しません。そこで重要になるのが、“風土づくり”です。 「副業していることを上司に言いづらい」「申請したら評価が下がるかもしれない」
「なんとなく副業=裏切りという空気がある」 こうした社員の心理的バリアは、副業制度を形骸化させてしまいます。制度を運用し、本当に社員の挑戦を後押しするには、「安心して申請・相談できる環境づくり」が必要不可欠なのです。
副業を「自己責任」で終わらせない仕組みを
制度やルールがあるにもかかわらず、副業にまつわるトラブルが起きる背景には、「自己責任」の一言で片付けてしまう企業の姿勢も関係しています。 たとえば、ある社員が副業先で健康を損なった、または副業の関係者とトラブルになった際、「それは本人の責任だから」と企業が一切対応しないのであれば、社員の信頼は失われてしまいます。 副業を解禁するとは、「社員の人生を多様に支援する」という宣言でもあります。その責任の一端を企業も共有するという姿勢を持ち、ルールと風土を一体的に整えていくことが、これからの組織には求められます。 副業制度を整えるということは、単に働き方を多様にすることではありません。それは、「社員が自律的にキャリアを切り拓く」ことを応援し、「個人の成長が組織の成長につながる」という価値観を体現することに他なりません。 副業時代のマネジメントは、管理や制限を前提とするのではなく、「信頼」「対話」「支援」を軸に展開していく必要があります。だからこそ、制度設計者やマネージャーこそが、“副業に対する正しい理解と柔軟な発想”を持つことが、風土づくりの出発点となるのです。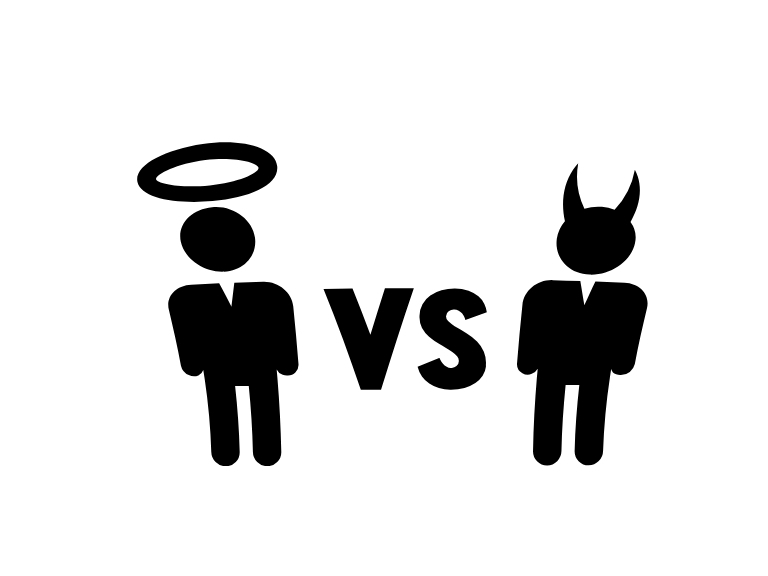
企業の副業制度導入事例
厚生労働省が公表する「副業・兼業の事例集」では、24社の取り組みが紹介されています。
以下では、その中から代表的な企業を取り上げ、制度設計・運用上の特徴や工夫点を明らかにします。
事例A:サイボウズ株式会社 — “複業可”文化の先駆者
■ 概要と制度の特長•サイボウズは、「100人いれば100通りの働き方があってよい」という理念を掲げ、2012年ごろから副業を認める体制を整備してきたとされます。
•2017年からは「複業採用」という枠組みも導入し、サイボウズでの業務自体を副業として関わる人材を外部からも受け入れる仕組みを作っています。
•社員が「申請すれば副業可」という透明性を担保しつつ、制度をオープンに運用してきた実績があります。 ■ 制度設計上の工夫・導入効果
•サイボウズでは「人事制度は変えるものではなく“足す”もの」という考え方が示されており、副業制度を既存制度に重ねる形で導入している点が特徴です。中小企業庁
•副業を禁止から解放することで、社員の当事者意識が高まったとされ、離職率の低下やモチベーション向上にも寄与していると、社長インタビューなどで語られています。
•また、複業採用を通じて、社外人材の視点を取り入れるという“組織風土への刺激”も事業戦略の一環として位置づけられています。
事例B:KDDI株式会社 — 部門横断・社内副業制度
■ 概要と制度の特長•KDDIは2020年6月から社内副業制度を開始し、社員が所属部門外のプロジェクトに携われるように制度設計しました。
•制度対象は、社員の本務時間のうち約20%を限度に活用できるような枠組みを置いており、部門間シナジー創出を狙っています。 ■ 制度設計上の工夫・導入効果
•社内副業制度を通じて、「組織間の壁を越えた人材活用」「ノウハウの横展開」「イノベーション創出」を目的に置いている点が特徴です。
•部門を越えて協働できる機会を社員に提供することで、これまで埋もれていたスキルや意欲のある社員を活性化する効果が期待されています。
•また、制度を通じて社員のモチベーション向上や社内の流動性強化に寄与したという報告もあります。
事例C:株式会社リコー — 2割ルールによる社内副業
■ 概要と制度の特長•リコーでは 2019年から社内副業制度を導入。社員は本務時間の2割程度を目安として異なる部署・プロジェクトに参加できる制度設計です。
•会社トップがこの制度に期待を示しており、社員の活動が活性化したとの社内評価も報じられています。 ■ 制度設計上の工夫・導入効果
•社員が新しい仕事やチャレンジに参加できる機会を制度として明示し、制度の“入口”と“枠”をきちんと設計している
•部門横断経験を得ることで、社員の視野拡大やキャリアの幅を広げる効果が期待されており、制度導入後、社内の動きが活発化したとされています。
事例D:株式会社 JTB — 労働時間管理モデル導入
■ 概要と制度の特長•JTBは副業禁止規定を明文化していなかったが、コロナ禍を機に副業ガイドラインを整備。リコー+2厚生労働省+2
•副業労働時間を「月 35 時間以内」と制限するルールを設け、過重労働の防止と実務管理の簡便化を図っています。厚生労働省+3リコー+3厚生労働省+3
•このような制度設計は厚生労働省が提唱する「簡便な労働時間管理モデル(管理モデル)」としても注目されています。厚生労働省+2厚生労働省+2 ■ 制度設計上の工夫・導入効果
•副業における労働時間管理負荷を抑制する目的で「管理モデル」に準拠した運用を導入した点が特筆されます。厚生労働省+2リコー+2
•社員にとっても「どこまで副業できるか」が明示されているため、安心感をもって申請できる制度設計となっています
事例E:株式会社ライオン — 持ち込み型副業制度と副業受入制度の併用
■ 概要と制度の特長•ライオンは「持ち込み型副業制度」と「副業受入制度」の2つを併用する制度設計を採用しています。
•「持ち込み型副業制度」は、社員が社外でやりたい業務を自ら持ち込む形式。新卒3年目以降の社員に適用される制度です。
•「副業受入制度」は、社外で特定のスキル・ノウハウを持つ人材を副業人材として社内業務に受け入れる枠組みです。 ■ 制度設計上の工夫・導入効果
•社員の“やりたいこと”を尊重する制度設計を前提に、制度の幅を持たせている点が特徴
•また、社外人材を副業として受け入れる制度を併用することで、社内外の知見を組織に取り込む戦略を持っている点も興味深い事例です

まとめ
副業をめぐる社会的な潮流は、もはや一部の先進企業だけの話ではなく、すべての企業が向き合うべき“新しい雇用の常識”となりつつあります。働き方改革やキャリア自律、多様性尊重の流れの中で、社員が会社の外でも自己実現を図ることは自然なこととなり、企業側もそれを拒むのではなく「どう付き合っていくか」が問われる時代に入りました。 しかしながら、副業を単に“解禁”するだけでは、企業と社員の双方にリスクをもたらしかねません。情報漏洩や競業、過重労働といったリスク、さらには評価制度とのねじれや職場の不信感の温床になることもあるでしょう。だからこそ今、企業には「副業をどうマネジメントするか」という視点が不可欠となっています。 副業解禁とは、“企業の外で何をしているかを監視する”ことではありません。それはむしろ、「社員がどう成長しようとしているのかを共に考え、応援する姿勢」を企業が持てるかどうかという、“信頼と共創”の試金石なのです。 副業という働き方を通じて、社員はより多様な経験とスキルを獲得します。企業側がこれを受け止め、制度と文化の両面から支援することができれば、それは単なる副業解禁を超えた、企業の魅力向上・人材定着・組織の成長へとつながるでしょう。 これからの時代、副業制度を「作るか否か」ではなく、「どのように信頼と整合性をもって運用するか」が企業の真価を問われるテーマとなります。副業を“リスク”ではなく、“戦略的な人材開発の機会”と捉える視点こそが、これからの人事に求められる新常識なのです。
【執筆者情報】
ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃
研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。