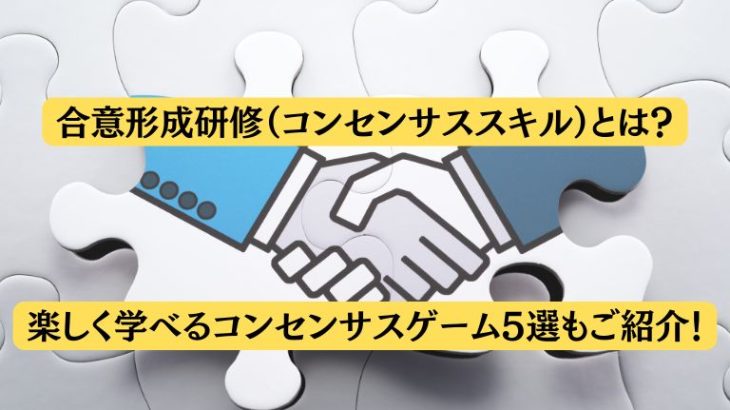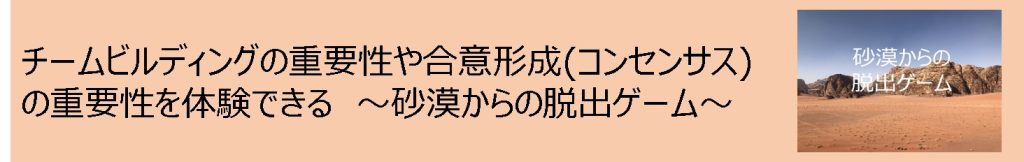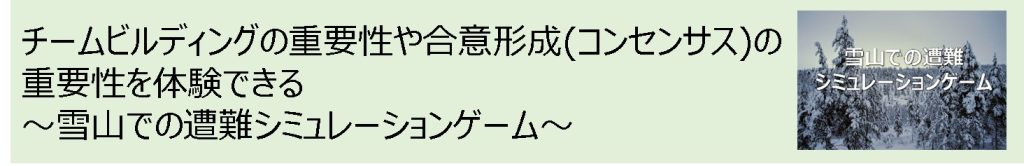目次
合意形成研修とは?
合意形成研修を楽しく学べるコンセンサスゲーム
コンセンサスゲームの流れ
コンセンサスゲームを行うときの注意点
おすすめのコンセンサスゲーム6選
コンセンサスゲームの導入事例のご紹介
合意形成研修とは?
合意形成研修を楽しく学べるコンセンサスゲーム
コンセンサスゲームの流れ
コンセンサスゲームを行うときの注意点
おすすめのコンセンサスゲーム6選
コンセンサスゲームの導入事例のご紹介
合意形成研修とは?
現代のビジネスシーンにおいて、個人のスキル以上に重要視されているのが「チームとして成果を出す力」です。その中核をなすのが合意形成(コンセンサス)スキルです。どんなに優れたアイデアを持っていても、メンバー同士の考えがすれ違い、方向性が一致しなければ、プロジェクトは前に進みません。特に多様な価値観や働き方が共存する今の時代、「誰かの意見に従う」のではなく、「全員が納得できる結論を導く」ことが求められています。合意形成研修は、そのような状況で発揮されるコミュニケーション力・傾聴力・論理的思考力・ファシリテーション力を総合的に鍛えるトレーニングです。 合意形成は単なる話し合いではありません。全員が意見を持ち寄り、対話を通して「共通の目的」を再確認しながら、最善の選択肢を模索していく「創造的プロセス」です。そのため、自己主張の強い人が主導したり、上位者の意見に盲目的に従ったりするような一方的な議論とは一線を画します。大切なのは「相手の意見を理解したうえで、自分の意見も伝え、より良い合意点を見出す」こと。まさに対立ではなく協働によって答えを生み出す力が問われるのです。 近年では、職場における意思決定のスピードと質を高めるために、多くの企業が合意形成研修を導入しています。例えば、会議で意見がまとまらない、部門間で優先順位が対立する、リーダーがメンバーの納得を得られない――こうした課題の背景には「コンセンサス形成のプロセス不足」が潜んでいます。合意形成研修では、こうした実務で起こりがちな場面を想定し、ワークショップ形式や体験型の“コンセンサスゲーム”を通して、実践的に学ぶことができます。 このような体験型の研修では、参加者は「自分の意見を整理して伝える」「相手の考えを尊重しながら調整する」「全体の合意を導く」という一連のプロセスを繰り返し体験します。単なる座学では得られない“気づき”が生まれ、他者と協働して問題解決に向かう面白さや難しさをリアルに実感できます。まさに、「対話から生まれる納得」を体験する学び――それが合意形成研修の最大の魅力です。

合意形成研修を楽しく学べるコンセンサスゲーム
コンセンサスゲームの目的
合意形成研修の中でも特に人気が高いのが、「コンセンサスゲーム」と呼ばれる体験型の学習手法です。コンセンサス(consensus)とは、単なる多数決ではなく、全員が納得し、同じ方向を向いて決定を下すプロセスのことを意味します。このコンセンサスの形成を、体験的に楽しく学ぶのがコンセンサスゲームの目的です。 多くの組織で課題となるのは、「話し合いをしても、結局一部の意見で決まってしまう」「声の大きい人に引きずられる」「みんなが遠慮して本音を言わない」といった“疑似合意”の状態です。このような状態では、会議終了後に不満が残り、後から軋轢が生じることもあります。コンセンサスゲームは、こうした問題を「安全な場」で疑似体験し、真の合意形成とは何かを学ぶことを目的としています。 たとえば代表的な「NASAゲーム(月面からの脱出)」では、宇宙船が月面に不時着したという架空の設定のもと、参加者一人ひとりが生存のために必要なアイテムを個別に順位付けします。その後、チームで話し合いながら最終的なグループ順位を決めていく過程を通して、「自分の考えに固執せずに意見を擦り合わせる力」「相手の根拠を聞き、再考する柔軟性」「最終的に納得して結論を出すスキル」を養います。ここでは「正しい答え」よりも、「どう合意に至ったか」というプロセスの質が学びの中心です。 コンセンサスゲームが合意形成研修に適している理由は、その“没入感”と“感情の動き”にあります。人は座学だけでは、自分の交渉パターンやチーム内での立ち位置に気づきにくいものです。しかし、ゲームの中で「自分の意見が通らない」「相手の話を聞きすぎて時間が足りない」「全員の納得が得られず決定が進まない」といった状況に直面すると、自然と感情が動きます。そこにこそ、気づきと成長のチャンスがあります。体験を通して“自分の意思決定の癖”に気づくことこそが、合意形成研修の本質なのです。 また、コンセンサスゲームは年齢や立場に関係なく、誰でも参加できるのが魅力です。新入社員研修や管理職研修、さらには異業種交流やリーダーシップ育成にも応用されています。特に近年では、「心理的安全性」や「ダイバーシティ&インクルージョン」といったテーマとの親和性が高く、多様な意見を尊重し合う文化づくりの第一歩として導入する企業も増えています。 たとえば、チーム内で意見が分かれる場面では、誰かの意見を「間違い」と決めつけず、「なぜそう考えたのか?」を丁寧に聞き取る姿勢が大切です。コンセンサスゲームでは、この“問いかける力”を自然と身につけることができます。自分とは異なる視点を理解しようとする姿勢は、合意形成だけでなく、リーダーシップやマネジメントにも直結する重要な資質です。 さらに、ゲーム形式で行うことで、参加者が主体的に楽しみながら学べる点も大きな特徴です。通常の研修では受け身になりがちな参加者も、ゲームになると積極的に意見を出したり、役割を分担したりと、自然に行動が活性化します。そのため、単に「合意形成の手法を理解する」だけでなく、コミュニケーションの実践練習の場としても大変有効です。終了後の振り返りでは、「普段の会議でも自分が無意識にこうしていた」「あの人の話し方がチームをまとめていた」など、参加者同士の気づきが共有され、学びが深まります。 つまり、コンセンサスゲームの目的は、単なる“楽しいレクリエーション”ではなく、合意形成の本質を体験を通して理解し、実務で活かせるスキルとして定着させることにあります。合理的な判断力、相互理解、そしてチーム全体で成果を生み出す思考を鍛える――それが、合意形成研修におけるコンセンサスゲームの真の価値なのです。
コンセンサスゲームの流れ
自分の考えをまとめる → グループディスカッション → 意見の発表
コンセンサスゲームは、単に話し合いを楽しむだけのアクティビティではなく、「思考のプロセス」と「対話のプロセス」を段階的に体験できる構造を持っています。多くの研修では、以下の3ステップを踏むことで、参加者一人ひとりの考え方や意思決定スタイル、チーム内での役割意識を深く理解することができます。① 自分の考えをまとめる(個人ワーク)
最初のステップは「個人の意思決定」です。与えられた課題(例:砂漠での遭難、月面からの脱出、災害時の避難行動など)に対し、自分一人の判断で最善だと思う選択肢を考える時間を取ります。 この段階では、他者の意見を聞かず、自分の論理・価値観・優先順位に基づいて答えを出すことが目的です。つまり、**「自分はなぜそう考えるのか」**を明確にするフェーズです。 ここで重要なのは、答えの正しさではなく、「自分の判断基準を言語化すること」。普段、会議やプロジェクトの中では、直感的に意見を出してしまうことが多いものですが、このプロセスを通じて、自分が何を重視して意思決定しているのか――安全性なのか、効率性なのか、協調なのか――といった自分の思考の軸を振り返る機会になります。
② グループディスカッションを行う(チームワーク)
次のステップが、コンセンサスゲームの核心である「グループディスカッション」です。個人でまとめた考えを持ち寄り、チーム全員で話し合いながら“ひとつの合意”を導き出すプロセスに入ります。 ここでは、単に多数決で決めるのではなく、全員が納得できる結論にたどり着くことがゴールです。そのため、相手の意見を尊重しながらも、自分の主張を根拠とともに伝えることが求められます。話し合いの中では、次のようなスキルが試されます。
✓相手の意見を途中で遮らず、最後まで聴く「傾聴力」
✓賛成・反対ではなく「なぜそう考えたのか」を問う「質問力」
✓感情的にならず、データや根拠に基づいて説明する「論理的思考力」
✓全員が参加できるように場を整える「ファシリテーション力」
ディスカッションの中で、意見が対立することは珍しくありません。しかし、それを避けるのではなく、対立の“理由”を丁寧に探ることで、より良い選択肢が生まれます。たとえば、「燃料を優先すべき」という意見と「水を優先すべき」という意見がぶつかったとき、互いの根拠を聞き合うことで「脱出には水より燃料が重要」「ただし生存期間を考慮すると水も必要」といった新たな視点が見えてくるのです。
つまり、コンセンサスゲームの醍醐味は「勝ち負け」ではなく、「違いから学びを得ること」にあります。最初は意見がバラバラだったチームが、次第に一つの方向にまとまっていくプロセスそのものが、まさに“合意形成の体験”なのです。
✓賛成・反対ではなく「なぜそう考えたのか」を問う「質問力」
✓感情的にならず、データや根拠に基づいて説明する「論理的思考力」
✓全員が参加できるように場を整える「ファシリテーション力」
③ 意見の発表を行う(振り返り・共有)
最後のステップは「チームの結論を発表する」フェーズです。グループで導き出した合意内容を、他のチームや全体に向けて共有します。ここで重要なのは、単に結論を述べるのではなく、どのような話し合いのプロセスを経てその結論に至ったかを振り返ることです。
「最初は意見が割れたが、根拠を出し合ううちに考えが整理された」
「誰かが意見をまとめてくれたことで方向性が見えた」
「声の小さい人の意見を拾ったことで、より良い結論になった」
こうした“プロセスの共有”が、学びを何倍にも深めます。講師やファシリテーターが正解と比較することで、チームの意思決定の傾向やコミュニケーションスタイルが明確になり、「私たちは論理的だが感情面に弱い」「全員の合意を取ろうとしすぎて時間配分を誤った」といった具体的な改善点が浮き彫りになります。
発表後のフィードバックでは、各チームの違いを比較することで、より客観的に自分たちの強みや課題を認識できます。たとえば、スピード重視型のチームと熟考型のチームを比べると、「どちらが正しい」ではなく、「目的に応じて使い分けることが大切」という気づきが得られるのです。
このように、コンセンサスゲームは、
(1)自分の考えを明確にする → (2)他者とすり合わせる → (3)学びを共有する
という3つのステップを通して、合意形成の本質である“納得のある意思決定”を体感的に学べる設計になっています。
単なる話し合いの練習ではなく、「チームとしてどう決めていくか」を体で理解する。これこそが、コンセンサスゲームが多くの企業研修で高い評価を受けている理由です。
「誰かが意見をまとめてくれたことで方向性が見えた」
「声の小さい人の意見を拾ったことで、より良い結論になった」
ゲームにご興味ある方はお問い合わせください。
コンセンサスゲームを行うときの注意点
否定しない・共同の目的意識を持つ・最終的に皆で納得する
コンセンサスゲームは、単に“話し合いをして答えを出す”というだけでなく、チーム内での信頼関係を築きながら最善の解を導く体験です。だからこそ、ゲームの進行中にどのような姿勢で臨むかが、学びの深さを大きく左右します。ここでは、合意形成の本質を体感的に理解するために大切な3つのポイントを紹介します。① 否定しない ― “意見”と“人”を分けて考える
コンセンサス形成の場で最も重要なのは、他者の意見を頭ごなしに否定しないことです。多くのチームでは、無意識のうちに「それは違う」「いや、こうすべきだ」と反射的に相手を否定してしまうことがあります。しかし、この瞬間に相手の発言意欲は低下し、チームの空気が閉じてしまいます。 合意形成の本質は、“正しい意見”を見つけることではなく、“納得できる意見”をつくり上げることにあります。相手の意見が自分と異なるときこそ、「なぜそう考えたのか」「どんな根拠があるのか」と問いかけ、理解する姿勢を持つことが大切です。 例えば、NASAゲームで「懐中電灯は不要だ」と主張する人と「暗闇での探索に必要」と主張する人がいた場合、ただ否定し合っても結論には至りません。しかし、「暗闇での活動がどれくらい想定されるか?」「太陽光がある時間帯との関係は?」といった具体的な質問を重ねることで、議論が前進します。相手の発言を“攻撃”ではなく、“情報源”ととらえることで、より建設的な対話が生まれるのです。
② 共同の目的意識を持つ ― “勝つ”のではなく“共に生き残る”
コンセンサスゲームでは、しばしば意見の対立が起こります。その際に忘れてはならないのが、「相手を説得して勝つこと」ではなく、「チーム全員で最善を見つけること」が目的であるという点です。つまり、“勝ち負け”の議論ではなく、“共創”の議論にするという意識が重要です。 たとえば、砂漠での遭難をテーマにしたゲームでは、メンバーの判断が命運を分ける設定になっています。水・地図・鏡などのアイテムをどの順番で優先するかを話し合う際、自分の意見に固執する人が多いと、チームはバラバラになります。しかし、全員が「生き残る」という共通の目的を再確認すると、話し合いのトーンが変わります。自分の意見を通すことよりも、「チームとしてどうすれば助かるか」を軸に考えられるようになるのです。 この“共同の目的意識”を持つことは、実際の職場でも極めて重要です。プロジェクトでは部署や立場が異なり、それぞれの利害がぶつかることもあります。しかし、共通のゴール――たとえば「顧客満足の最大化」「プロジェクト成功」「チームの信頼関係構築」など――を明確に共有することで、対立が協働に変わります。コンセンサスゲームは、まさにその“目的意識の再統一”を体験的に学ぶ場でもあるのです。
③ 最終的に皆で納得する ― “結論”よりも“納得のプロセス”を重視
コンセンサス形成では、「全員が納得して決めること」が最終ゴールです。ここで重要なのは、「納得」と「同意」は違うという点です。同意とは「仕方なく賛成する」ことであり、納得とは「理由を理解して受け入れる」こと。見た目には同じ“賛成”でも、その中身には大きな違いがあります。 コンセンサスゲームの中では、時間制限や意見の対立などから、つい「もうこれでいいか」と妥協してしまう場面があります。しかし、その“妥協”はゲームの本質を損ねてしまいます。真の合意形成とは、全員が「なぜこの結論に至ったのか」を理解し、「自分もその一部を担っている」と感じられる状態です。 講師やファシリテーターが進行する際も、「誰が提案したか」ではなく、「なぜその選択が合理的なのか」を確認しながら進めることで、参加者の納得感が高まります。議論の中で多数派の意見が採用されることもありますが、その際も少数派の考えをきちんと扱い、「この意見も検討した結果、こちらを選んだ」というプロセスの透明性を示すことが大切です。 納得感を伴った結論には、“当事者意識”が生まれます。自分が関わって導いた決定だからこそ、実行に移す意欲が湧くのです。これはまさに、実際の職場における意思決定と同じ構造です。コンセンサスゲームは、単なる模擬体験ではなく、職場での合意形成のリハーサルとして大きな価値を持ちます。
信頼・尊重・共創が、合意形成の3原則
コンセンサスゲームの成功は、「否定しない」「共同の目的を持つ」「全員が納得する」という3原則の上に成り立っています。これらを意識して進めることで、チームの中に心理的安全性と信頼関係が生まれ、活発で前向きな議論が可能になります。 ビジネスの現場でも、結論よりプロセスを大切にする姿勢が求められる時代。コンセンサスゲームは、こうした新しい組織コミュニケーションのあり方を体験的に学ぶ最高の教材なのです。おすすめのコンセンサスゲーム6選
合意形成を楽しく、そして実践的に学べるコンセンサスゲームは数多く存在します。その中でも特に人気が高く、企業研修や教育現場で繰り返し採用されているのが次の5つのゲームです。いずれも共通しているのは、「正解よりも、どう合意に至るか」というプロセス重視の学びであること。ここでは、それぞれの特徴と学べるスキルを紹介します。
NASAゲーム(月面での不時着)
もっとも代表的なコンセンサスゲームといえば「NASAゲーム」です。参加者は、月面に不時着した宇宙船の乗組員という設定で、手元に残された15のアイテムを重要度順に並べる課題に挑戦します。個人で順位を付けた後、チーム全員で話し合いながらグループとしての最終順位を決定。最後にNASAの公式解答と照らし合わせて結果を確認します。 このゲームでは、「自分の考えに固執せず柔軟に再考する力」「根拠を持って意見を伝える力」「チーム全体で結論を導く対話力」が試されます。特に、リーダーがどのように議論を整理し、全員の意見を引き出すかがポイントとなり、ファシリテーション力やリーダーシップのトレーニングにも最適です。
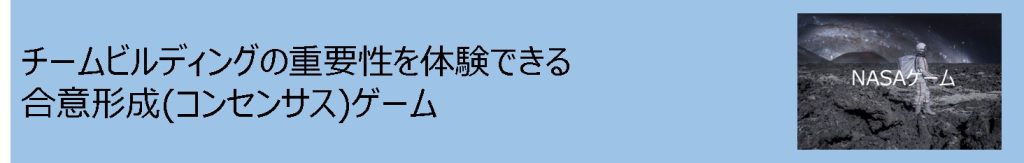

砂漠からの脱出ゲーム
こちらも古典的な人気を誇るコンセンサスゲーム。舞台は灼熱の砂漠。飛行機が墜落し、生存者である参加者たちは、限られた物資の中からどのアイテムを優先して持ち歩くかを議論します。NASAゲームと同様に、個人判断とチーム合意の差を体験できる構成です。 このゲームの特徴は、「生死に関わるリアルな設定」が議論をより真剣なものにする点です。人によって価値基準が大きく分かれるため、意見の衝突が生まれやすく、説得力や論理的思考、そして相手への共感力をバランスよく養えます。特に、営業職やプロジェクトチームのメンバーにとって、限られた条件下で最適な判断を導く練習として効果的です。
雪山遭難シミュレーションゲーム
「雪山遭難シミュレーションゲーム」は、極寒の雪山で遭難した登山チームが、下山ルートや持ち物の優先順位を話し合う設定です。参加者は“限られた時間”と“リスクの高い環境”の中で判断を迫られます。 このゲームの魅力は、「時間制限」と「命の危険」というプレッシャーの中での意思決定を体験できる点にあります。冷静な判断力を保ちながら、感情的な対立をどう収めるかが鍵となり、危機下のリーダーシップや冷静な意思決定力、合意形成のスピード感を磨くことができます。管理職研修や危機対応トレーニングとしても人気が高く、現実のビジネス現場に直結する学びが得られます。
マリン・サバイバルゲーム
「マリン・サバイバルゲーム」は、海難事故に遭遇し、救命ボートで漂流するというシナリオの中で、チームで生き残るためにどのアイテムを優先するかを合意していく体験型のコンセンサスゲームです。舞台は広大な海上。限られたアイテム(食料、釣り竿、鏡、救命信号など)をどの順番で活用すべきかを議論しながら決定していきます。 このゲームでは、まず参加者一人ひとりが個人でアイテムの重要度を順位づけします。その後、4~6名のチームに分かれてディスカッションを行い、全員が納得できるチームの最終順位を導き出すのが目的です。最後には模範解答(海上救難専門家の判断)と比較し、個人順位・チーム順位の差を振り返ります。 学びのポイントは、「合意形成は多数決ではない」という点です。海上という非日常的な状況の中で、個人の価値観が大きく分かれるため、メンバー間で自然に意見の対立が生まれます。その中で、相手の意見を否定せず、根拠を聞き出し、より合理的な判断を模索する力が鍛えられます。また、結論に至るまでの「話し合いの質」が、最終結果の良し悪しを左右するため、傾聴力・質問力・説明力などの基本的なコミュニケーションスキルを総合的に伸ばすことができます。 さらに、マリン・サバイバルでは「制限時間」や「命を守る」という共通目的が設定されているため、チームメンバー全員が自然と協力的な姿勢を取るようになります。このプロセスを通じて、“グループからチームへ”と変化する瞬間を体感できるのが最大の魅力です。 研修では、新入社員研修や若手層のチームビルディング、また部門横断プロジェクトの関係性づくりにも効果的。楽しみながらも「協働と納得の意思決定」をリアルに学べる定番のコンセンサスゲームです。
船長の決断
「船長の決断」は、旅客船の船長となった参加者が、突発的な事故や沈没の危機に直面した際に、どのような行動を取るべきかを判断する合意形成ゲームです。 与えられたシナリオには、「火災発生」「乗客の混乱」「通信機器の故障」などの緊急事態が次々と登場し、どの処置を優先すべきかを10項目程度の選択肢の中から順位づけします。 最初に個人で判断した後、チーム全員で議論を行い、船として最も多くの命を救うための合意を形成します。最終的に模範解答(危機管理専門家の視点)と比較し、どの判断が合理的だったのかを検証します。 このゲームの特徴は、単なるサバイバルではなく、**「限られた情報と時間の中で最適な意思決定を行う」**という、現実のビジネス現場に近い構造にあります。リーダーシップとチームワークの両立が求められ、特に「リーダーの指示待ちにならない議論の進め方」や「役割分担を明確にして時間内に結論を出す」重要性が体験的に理解できます。 また、危機的状況では意見の衝突だけでなく、感情的な動き(焦り・不安・責任感)も生じやすくなります。そのため、「冷静に議論を整理する力」や「優先順位の決め方」「チーム全体の納得感を得る方法」といった、実務にも直結するスキルを鍛えることができます。 研修としては、中堅社員や管理職、リーダー層に特におすすめです。緊急時対応やリスクマネジメント研修にも応用でき、合意形成+危機判断+リーダーシップを同時に学べる実践的なプログラムです。
商談の達人ゲーム
「商談の達人ゲーム」は、企業間交渉をテーマにした営業・交渉力強化型のビジネスシミュレーションゲームです。 参加者は自動車メーカーや部品サプライヤーなど、複数の企業に分かれ、それぞれが異なる条件・目標・リソースを持ってゲームを進行します。目的は、他チーム(取引先)との交渉や条件調整を通じて、最も高い成果を上げることです。 ゲームでは、「原価」「納期」「数量」「品質」「契約金額」などの要素が複雑に絡み合い、チームは自社の利益を守りながら、相手にも納得してもらえる条件を探ります。単なる駆け引きではなく、【Win-Winの合意形成を目指す“交渉型コンセンサスゲーム”】として構成されているのが特徴です。 商談の過程では、「自分たちの主張を通す交渉」だけでなく、「相手のニーズを引き出すヒアリング力」「提案を論理的に構築する力」「社内の意見をまとめる力」など、実際のビジネス現場で必要とされるスキルが総合的に求められます。さらに、交渉が失敗した場合の損失や、過剰な譲歩による不利益も体験できるため、交渉のリスクマネジメントもリアルに学ぶことができます。 このゲームは、営業担当者だけでなく、購買・企画・管理職など、社内外の利害調整を担うすべての職種に有効です。ゲーム終了後には、交渉過程を振り返りながら「なぜこの合意に至ったのか」「他チームはどう戦略を立てたのか」を共有することで、実務への転用が可能になります。 まさに「商談の達人ゲーム」は、理論と実践をつなぐ交渉スキル研修として、合意形成研修の中でも高度な応用編といえる内容です。

状況に応じて選べる「最適なコンセンサス体験」
このように、コンセンサスゲームには「サバイバル型」「ビジネス型」「リーダーシップ型」など多様なテーマがあり、目的に応じて最適な内容を選ぶことが可能です。 若手・新入社員には「NASA」「砂漠」など、基礎的な合意形成体験中堅社員・リーダー層には「雪山」「無人島」など、判断力・調整力を重視した内容
管理職・営業職には「マーケット交渉」など、実務に即した意思決定体験 どのゲームにも共通するのは、「正解」を探すのではなく、「納得できる結論を導く力」を養うという点です。コンセンサスゲームは、楽しく学びながらチームの関係性を深め、組織としての意思決定力を高める、まさに“実践型コミュニケーション研修”なのです。
ゲームにご興味ある方はお問い合わせください。
コンセンサスゲームの導入事例のご紹介
―「砂漠からの脱出」「NASAゲーム」「雪山遭難シミュレーション」の実施事例― コンセンサスゲームの魅力は、理屈ではなく“体験”を通じて学べる点にあります。ここでは、実際に企業や学校、団体で実施された3つの代表的な事例を紹介します。いずれも参加者が「自分の意見を見直す」「他者の考えに耳を傾ける」「全員で納得のいく答えを導く」プロセスを通じて、合意形成の難しさと奥深さを実感した研修です。
事例①:一般社団法人寝屋川青年会議所
この研修は、70名規模で「NASAゲーム」(月面不時着という設定のコンセンサスゲーム)を実施したものです。 導入背景として、コロナ禍で委員会メンバー間の交流が減少し、メンバー同士の絆を深め、会議を活性化させたいという課題があり、 研修では、メンバー各自がまず個人でアイテムの優先順位を考え、その後チームで話し合いながら共通解を出すという典型的な合意形成プロセスが取られました。 参加者からは、
「久しぶりにリアル開催ができて、皆が楽しそうに議論していた」という声があり、また「組織づくりへのヒントになった」という質問も複数出たとされます。
この事例では、ゲームを通じて「個人の判断」と「チームの合意」の差/合意形成プロセスの難しさと価値を体感する設計となっており、地域団体という横断型のメンバーにも適した設計となっています。
事例②:株式会社栄光会
こちらは、接骨院・整体院・デイサービス運営の企業が50名(10チーム)を対象に、「砂漠からの脱出ゲーム」(砂漠遭難設定)を導入した事例です。 目的としては、経営計画発表会の場で「各店舗を一つに」「会社としてまとまる」機会を作ることが挙げられていました。 ゲーム概要として、「12個のアイテムを、重要度順に順位付け→個人→チーム→模範解答との比較」という流れが採られ、10チームの中で優勝チームの誤差点が21点という記録も紹介されています。 この事例の特徴は、経営イベント(発表会)という“公式な場”でゲームを位置づけ、「ゲームで学ぶ体験+その後の実務意識づけ」という流れを強く意識していた点にあります。ゲームを“楽しいだけ”にせず、組織としての合意形成・チーム化を目的としていた点が注目されます。

事例③:フェリタス社会保険労務士法人
この事例も「NASAゲーム」を導入し、対面+オンライン混在型で実施された点が特徴です。 設定・内容は、宇宙飛行士が月面に不時着するというストーリーのもと15個のアイテムを優先順位付けし、チームで合意を導き、模範解答との誤差を競う流れ。 参加者の満足度として、
ゲーム満足度:4.4/5点
講師説明満足度:4.4/5点
というアンケート結果になりました。
この実施では、遠隔勤務メンバー含むハイブリッド環境で行われ、グループワークやブレイクアウト機能を使った議論が活性化していた点が、「オンライン/ハイブリッドな環境下でもコンセンサスゲームが有効である」ことを示す実例です。
講師説明満足度:4.4/5点

導入の効果と次のステップ
これらの事例では、参加者が「自分だけで判断するのではなく、メンバーと価値観をすり合わせる」「他者の根拠を聞きながら再検討する」という体験を得ています。特に、店舗展開企業や横断的な委員会といった“複数部門・拠点横断”のチーム構成では、ゲームを通じて一体感や対話のきっかけを作ることが可能です。 また、オンライン/ハイブリッド実施の可能性が高まっていることから、リモートチームや全国拠点展開企業でも実施ハードルが低くなっています。さらに、満足度の公開やスコア比較構造があるため、「研修投資の効果検証」が行いやすいこともメリットです。 次のステップとしては、ゲーム後の「業務・会議での合意形成プロセス改革」へ接続する設計がカギです。例えば、研修後に「会議での合意所要時間」「発言者数の偏り」「決定後の再協議率」などのKPIを設定し、ゲーム体験を組織文化・仕組み改革に繋げることが推奨されます。
まとめ
合意形成(コンセンサス)研修は、単なる「話し合いの練習」ではなく、「チームで納得を生み出す力を育てる“体験型の学び”」です。個人の主張を押し通すのではなく、互いの考えを理解し合い、共通の目的のもとで最善策を導き出す――このプロセスこそが、現代の組織に最も求められるスキルといえるでしょう。 今回紹介した各種コンセンサスゲーム(NASAゲーム、砂漠からの脱出、雪山遭難シミュレーション、マリン・サバイバル、船長の決断、商談の達人ゲーム)は、いずれも楽しみながら実践的に“合意形成の本質”を体感できるよう設計されています。特に、ゲームの中で意見が対立したり、時間に追われたりする状況は、まさに実際の職場の縮図。そこにこそ、対話・傾聴・リーダーシップ・柔軟な思考など、組織で成果を出すための行動原理が凝縮されています。 さらに、ビジネスゲーム研究所(株式会社情熱Factory)では、企業規模や業種、参加人数に応じて最適なゲーム設計とファシリテーションを提供しています。50名規模の研修から200名を超える大規模イベントまで対応可能で、オンライン実施やハイブリッド型研修も多数実績があります。 “正解のない時代”を生き抜くためには、上司の指示に従うだけではなく、自ら考え、周囲と合意を形成しながら前に進む力が必要です。コンセンサスゲームは、その力を安全で楽しい環境の中で磨ける最適な研修です。組織の結束力や意思決定力を高めたい企業・団体の方は、ぜひビジネスゲーム研究所の合意形成研修を体験してみてください。
【執筆者情報】
ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃
研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間50登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。
合意形成(コンセンサス)ゲームのお問い合わせ