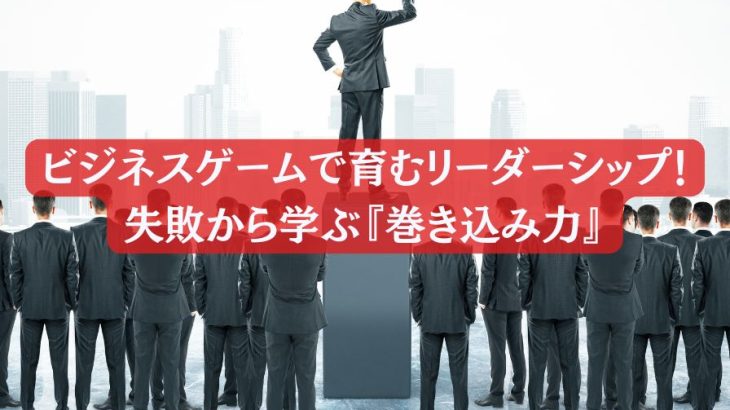•周囲のサポートを得るために、ビジョンや目標の共有を的確に行う
•自分だけが先走るのではなく、メンバーが主体的に動けるよう環境を整える こうしたアクションを総称して、「周囲を巻き込む力」といえます。しかし、実務だけでこれを身につけるのは容易ではありません。なぜなら、日常の業務は目の前のタスク処理で手一杯になりがちで、失敗したくても失敗できない(=リスクが高い)状況も多いからです。 この課題を解決するために注目を集めているのが、「ビジネスゲーム」を活用したリーダーシップ研修です。ゲームという仮想のビジネス環境であれば、一定のルールや競争要素がある中で、失敗しても実害が少なく、すぐに振り返りをして学びを深められます。本コラムでは、ビジネスゲームの特性や具体的な失敗例を交えながら、「巻き込み力」を育むためのヒントを詳しく解説していきたいと思います。

ビジネスゲームとリーダーシップ研修の親和性
(1) 模擬体験によるリスクフリーな挑戦
ビジネスゲームは、会議室やオンライン上で実施する“模擬的なビジネス体験”です。たとえば「会社経営シミュレーション」や「新規事業立案ゲーム」など、多種多様なテーマが存在します。これらのゲームの特徴として、
1.失敗しても実損がない
実際のビジネスであれば、不採算プロジェクトの立ち上げや無謀な投資は会社のリスクに直結します。しかしゲームであれば、仮想通貨やポイントなど、実害のない資源を使います。そのため、普段はできない大胆な戦略を試したり、あえてリスクを取る行動をしてみることが可能です。2.すぐに結果が出て、フィードバックが得られる
多くのゲームは短期間(数時間〜数日)で成果がはっきり見えます。「値段設定を変えたら売上が急増した」「生産コストを抑えた分、品質が低下して評判が悪くなった」など、リアルな感覚で成功・失敗を体感できます。3.仮説検証サイクルを繰り返すことで学びが深まる
「うまくいかなかった原因は何か?」「次はどう戦略を変えるか?」といった振り返りを、1回の研修内で何度も試すことができます。こうしてPDCAサイクル(計画→実行→振り返り→改善)を素早く回すことで、短時間に多くの知見を得られるのです。
(2) 他者とのインタラクションを通じた学び
ビジネスゲームの多くは、個人プレイではなくチームプレイで進めます。チームで議論して方針を決めたり、他チームとの競争・交渉を行ったりすることで、自然とコミュニケーション能力やリーダーシップの発揮が必要になるわけです。
【チーム内での議論】
「誰がリーダーシップを取って指揮を執るのか」「メンバーが役割をきちんと理解し合っているか」など、ゲームの流れに応じてリーダーシップのあり方が可視化されます。気づかないうちに独善的になっているリーダーや、意見を言わずに傍観してしまうメンバーなど、リアルな人間模様が浮かび上がることも多いでしょう。【他チームとの駆け引き】
複数チームが同時にゲームを進める場合、競争関係になる場面があります。市場シェアの奪い合いや、場合によっては交渉や提携をするケースもあるでしょう。ここでは、状況把握や情報戦略だけでなく、「他チームを味方につける巻き込み方」「相手を説得するコミュニケーション力」が試されます。実社会のビジネスとほぼ同様のドラマが展開するため、受講者は真剣に取り組むようになります。(3) 楽しさ・没入感で学習効果を高める
人は本来、ゲームに対して「楽しい」「挑戦したい」「勝ちたい」という心理を持っています。これが学習として最適に働くのがビジネスゲームの強みといえます。
【エンターテインメント性が高い】
普段の座学研修や講義スタイルでは、どうしても受講者が受け身になりがちです。それに対してゲームでは、与えられる課題やトラブルをクリアしようと自発的に動くため、自然と没入感が高まっていきやすいのです。【学んだスキルを即実践しやすい】
たとえば「リーダーシップの理論」を頭で理解していても、実際にどのようなコミュニケーションを取ればいいのかは、経験しないとつかみにくいものです。ビジネスゲームは、頭の理解と行動を同時に体験できるため、「腹落ち感」が得られやすくなります。
ビジネスゲームで起こりがちな失敗例
ビジネスゲームは、チーム内でのやり取りや意思決定プロセスがリアルに露呈するのが特徴です。ここでは、ゲームでありがちなリーダーシップ上の失敗パターンをご紹介します。実務でもよく似た状況が起こりやすいため、ぜひ対策のヒントにしてみてください。
(1) 指示命令ばかりでメンバーの声を拾わない
リーダーが「自分の考えが正しい」と決めつけ、ほかのメンバーに意見を求める前に指示や命令を出してしまうケースです。たとえば、次のようなシーンがよく見られます。•ゲーム開始直後、リーダーが「まずこれをやろう」と一方的に役割を割り振る
•メンバーが「こういうやり方はどうか」と提案しても、リーダーが「いや、それは無理だ」と聞く耳を持たない
•何らかのトラブルが起きた際も、リーダーひとりで対策を考え、勝手に進めてしまう
こうなると、他のメンバーは自分のアイデアを出すモチベーションを失ってしまい、指示されたことだけをこなす「受け身」の状態に陥ります。結果的に、ゲーム内では新たな視点やアイデアが生まれず、チーム全体としての成果が伸び悩むのです。
•メンバーが「こういうやり方はどうか」と提案しても、リーダーが「いや、それは無理だ」と聞く耳を持たない
•何らかのトラブルが起きた際も、リーダーひとりで対策を考え、勝手に進めてしまう
(2) 役割分担が曖昧でチームが混乱する
特に、リーダー自身がリーダーシップを十分に発揮しない場合に起こりがちです。「これは誰が担当する?」「ゴールは何だっけ?」といった基本的なことが不明瞭なまま、時間だけが過ぎてしまうことがあります。
•チーム内の人数が多いほど、役割分担の曖昧さが混乱を招きやすい
•「Aさんがこれをやると言っていたけど、やっていなかった」などの認識ズレが生じ、無駄な時間と労力を消費する
•失敗した際に、責任の所在もわからず、原因追及や改善策が曖昧になる
このように、リーダーシップやマネジメントが機能しないと、わずか数時間のビジネスゲームでも大きな混乱が生じます。その混乱こそ、研修では大きな学習ポイントになりますが、当事者として経験すると焦りやストレスを強く感じるはずです。
•「Aさんがこれをやると言っていたけど、やっていなかった」などの認識ズレが生じ、無駄な時間と労力を消費する
•失敗した際に、責任の所在もわからず、原因追及や改善策が曖昧になる
(3) コミュニケーション不足によるリスク共有の失敗
ゲームの中には「他チームの動向や市場情報がゲームの勝敗を大きく左右する」パターンがあります。たとえば、ゲームの世界観で「原材料の価格が高騰するかもしれない」「他チームが値下げ戦略に出るかもしれない」と予測されている場合、リーダーやチームメンバーはこまめに情報を取りに行き、戦略を立て直す必要があります。•周囲とのコミュニケーション不足で、重要な情報を見逃す
•最初に立てた計画通りに進めたいがために、環境の変化に応じた修正を怠る
•「もっと早く知っていれば対応できたのに……」という後悔で終わる
こうしたコミュニケーション不足は、現実のビジネスでも同じように大きなリスクとなります。プロジェクトチームが組織内外の関係者と連携を取らずに進めてしまい、気づいたときには手遅れになっていた・・・という事態を防ぐには、普段からの情報共有と周囲を巻き込む姿勢が欠かせません。
•最初に立てた計画通りに進めたいがために、環境の変化に応じた修正を怠る
•「もっと早く知っていれば対応できたのに……」という後悔で終わる
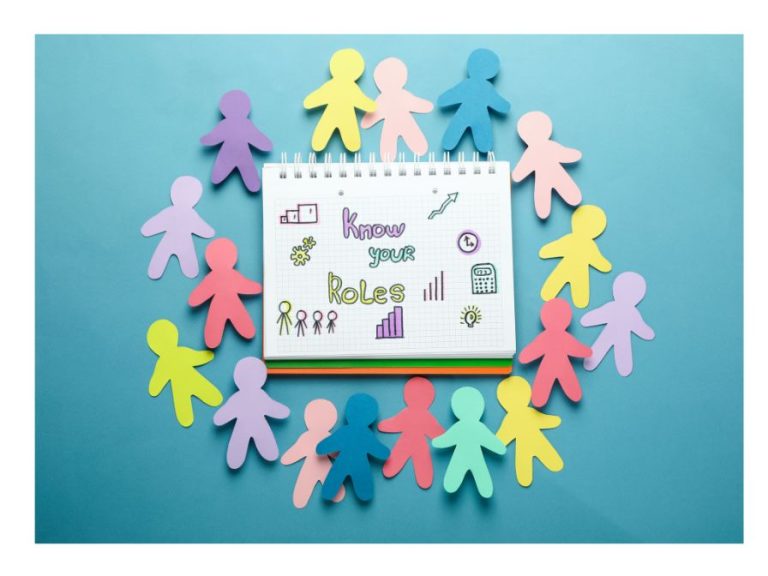
失敗から学ぶ「巻き込み力」の重要性
前章で挙げたビジネスゲームにおける失敗例は、実は組織運営やプロジェクト推進においても日常的に起こり得ることばかりです。そこで、こうした失敗をどう活かし、いかに周囲を巻き込む力を養っていくか――ここにビジネスゲームを取り入れる研修の真価があります。
(1) 周囲を巻き込むことで見える視点の広がり
リーダーひとりの経験やスキルだけでは、常に最適解を導き出すことは難しいものです。なぜなら、ビジネス環境の変化は多様かつ予測不能であり、個人の視野には限界があるからです。 •チーム全員の「気づき」や「アイデア」を結集できるたとえば、財務に強い人、マーケティングに詳しい人、現場目線を持っている人など、多様なバックグラウンドを持つメンバーがいるほど、チームとしての総合力は高まります。リーダーが巻き込み力を発揮して意見を吸い上げると、情報量が増え、より多角的な視点で戦略を検討できるようになります。 •「自分の考えが必ずしも正解ではない」という謙虚さを持てる
巻き込み力を発揮するうえでは、リーダーの「他者を尊重する姿勢」が欠かせません。どれほど経験豊富なリーダーでも、周囲に耳を傾けることで初めて見える盲点があるのです。
(2) メンバーの主体性と協力を引き出す
巻き込み力を発揮するリーダーは、メンバーにただ命令や指示を出すだけでなく、**「当事者意識を持てるよう環境を整える」**ことに注力します。 •役割やミッションを共有し、権限を委譲する「このプロジェクトの成功はあなたが鍵を握っている」「あなたの提案が重要だ」と伝えれば、メンバーのやる気は自然と高まります。特にビジネスゲームのような仮想環境では、リーダーがうまく役割を割り振り、メンバーを信頼して任せるほど、チーム全体がスムーズに動き出します。 •チーム内の心理的安全性が高まる
メンバーが「失敗を恐れずに意見やアイデアを出せる」と感じられるようになると、本音ベースの意見交換が進みます。結果的に、最初は小さなアイデアでも、メンバー同士でブラッシュアップするうちに大きな成果やイノベーションにつながる可能性が高まります。
(3) 失敗をチャンスに変えるチームづくり
ビジネスゲーム研修では、どうしても「失敗」のシーンに直面しやすくなります。しかし、その失敗を振り返って改善策を練る過程こそ、巻き込み力を養う最大のポイントです。 •「何が悪かったのか」「どうすれば改善できるのか」をチーム全員で考えるリーダー一人が反省するだけではなく、「誰が、どの部分で、どういった対策を打つか」をチームとして共有します。これにより、メンバー全員が“自分事化”して動くようになります。 •次のラウンドで即トライ&エラーを実践できる
ゲーム形式の場合、失敗後すぐに「次の施策」を試せるケースが多いです。ここで「周囲を巻き込んだ改善策」を導き出せると、実務への応用が一気に具体化しやすくなるのです。

「巻き込み力」を高める具体的な方法
ここからは、実践的なレベルで巻き込み力を高めるための方法をご紹介します。ビジネスゲームの場面だけでなく、日常の業務でも応用できるポイントばかりです。
(1) ビジョン・ゴールの共有
組織やプロジェクトの最終的な目標が、メンバー全員に十分に伝わっているでしょうか? •目標を数値化・具体化する例として、売上目標だけでなく、「何をどの期間で、どんな方法で達成するか」を言語化すると、メンバーが自分のタスクや役割をイメージしやすくなります。 •なぜその目標が重要なのか「ストーリー」を伝える
「売上を増やしたいから」だけでは、メンバーはモチベーションを高く維持しにくいことがあります。「市場を拡大して、業界に新しい価値を提供したい」「この新規事業で社会課題を解決したい」など、チームが一致団結できる物語をリーダー自身が語れると強いです。
(2) 対話を重視したコミュニケーション
「巻き込む」ためには、一方向の情報伝達ではなく、常に対話を通じて意見の交換をすることが欠かせません。 •ショートミーティングやブリーフィングの活用毎朝5〜10分程度の短い時間で、前日の成果と課題を共有し合うだけでも、メンバーの気づきを促しやすくなります。ビジネスゲーム中でも、各ラウンドごとにミーティングを挟むことで状況をすばやく共有し、戦略変更の機会を逃しにくくなります。 •メンバーの意見を引き出す質問力
「何か意見ある?」と大まかに尋ねるだけでは、遠慮してしまうメンバーもいます。そこをリーダーが「〇〇の課題をどう捉えている?」「もし××をやるなら、どんなリスクがあると思う?」と具体的に質問することで、本音を引き出しやすくなります。
(3) 役割と責任を明確化する
チームで行動する際、誰が何を担うかが曖昧だと、成果が出にくいだけでなく、メンバー自身も力を発揮しにくくなります。 •当分野と期待する成果をはっきり伝えるたとえば「Aさんはマーケティング全般を見て、Bさんは財務管理と予算配分を最適化する」など、責任範囲を具体的に設定します。併せて「どのタイミングで、どんな形でリーダーに報告するか」まで決めておくと、ゲーム中も実務中もスムーズに進められます。 •“任せっぱなし”ではなく適度なサポートを行う
役割を明確にしたら、あとは本人にすべて委ねるのが理想的ですが、状況によっては助言や調整が必要です。定期的に進捗を確認し、必要に応じて周囲を巻き込みながらサポート体制を整えることで、メンバーが孤立するリスクを回避できます。
(4) フィードバックサイクルの強化
巻き込み力を高めるためには、「メンバーが自分の行動を変えたい」「スキルアップしたい」と思えるようなフィードバックの仕組みが重要です。 •小さな成功体験を見逃さないゲームの中で「ちょっとした工夫がうまくいった」という事例は、チーム全員で共有し称賛すると、メンバー同士が互いのチャレンジを後押しし合います。 •失敗からの学びを素早く共有する
上手くいかなかった施策があった場合、すぐに「何が原因だったか」「今後はどう改善するか」をメンバーと議論し合います。リーダーが“責任追及”ではなく“学習の機会”というスタンスでフィードバックを行うと、メンバーが積極的に議論に参加しやすくなるでしょう。

ゲーム内での学びを実務に活かすには
ビジネスゲームで得た気づきや成長の芽を、いかに実務に落とし込むか。ここでしっかりと実務への接続を図ることができれば、研修効果は格段に高まります。
(1) 研修後のフォローアップ体制
「研修が終われば学びも終了」では、せっかくの発見が生かされません。 •ゲーム内で気づいたポイントをリスト化し、現場で試すたとえば、「チームミーティングの頻度を上げたらうまくいった」「意思決定にメンバーのアイデアを取り入れたら予想外の結果が出た」などの経験を、具体的な行動プランとして書き留め、実務で実践してみましょう。 •定期的に振り返り会を開く
「1ヵ月後」「3ヵ月後」など、区切りを決めて研修参加者同士で振り返りを行うことで、行動変容が進んでいるかを確認できます。その際、上司や人事部がサポート役となり、アドバイスや追加研修を検討する仕組みがあると理想的です。
(2) チーム文化としての「巻き込み力」浸透
巻き込み力は、リーダーだけが持っていればいいというものではありません。むしろ、メンバー全員が周囲を巻き込みながら主体的に行動するチーム文化こそが、強い組織をつくります。 •メンバー同士が学び合うコミュニティづくりチーム内で「こういうことをやってみたらどうか?」と提案し合いながら、互いにサポートする文化が根付くと、自然と組織全体が協働的になります。ビジネスゲーム研修をきっかけに、オンラインのコミュニティやランチ会など、メンバー同士が横のつながりを保てる仕組みを作るのも有効です。 •巻き込み力を評価・報奨制度に反映する
リーダーシップや周囲を巻き込む姿勢がしっかり評価される環境であれば、人は行動変容を起こしやすくなります。「成果」だけでなく「プロセス」も評価する方針を打ち出すことで、リーダー以外のメンバーも自ら巻き込み力を発揮しようと前向きになります。
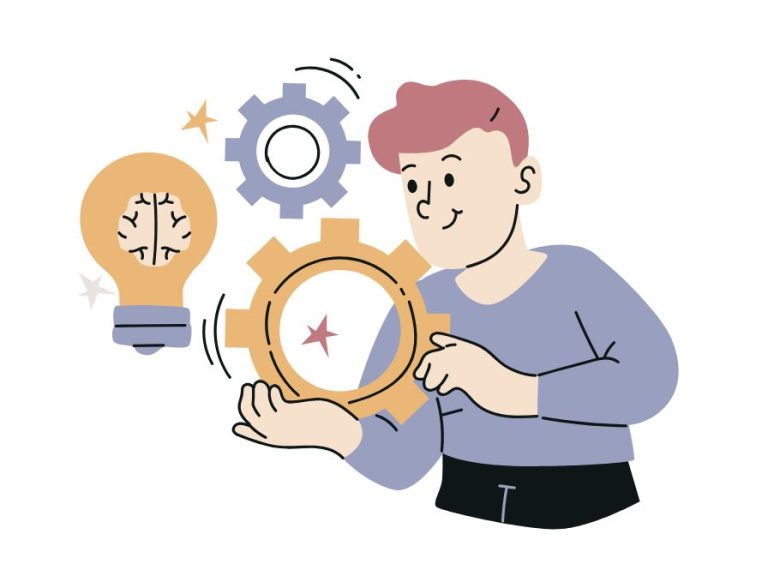
まとめ
ビジネスゲームは、単なる“遊び”ではなく、「行動を通じた気づき」を得るための優れた手段です。仮想空間での失敗や成功が、実務の縮図として強いインパクトをもたらし、それをチーム全員で振り返ることでリーダーシップや巻き込み力の本質を体感しやすくなります。 巻き込み力は一朝一夕で身につくものではありません。日々の業務でメンバーを巻き込み続け、失敗しながら改善を重ねる姿勢が大切です。また、巻き込み力を「リーダーだけのもの」にしないでください。メンバー全員が自発的にアイデアを出し合い、周囲の人を巻き込み合うようになれば、組織全体の成長スピードは格段に上がります。 本コラムを通じて、ビジネスゲームを活用したリーダーシップ研修の可能性と、失敗から学ぶ巻き込み力の重要性を少しでも感じ取っていただければ幸いです。実際にビジネスゲームを取り入れてみる際は、ぜひ今回のポイントを押さえつつ、「学んだことを現場でどう活かすか」を意識して取り組んでみてください。それこそが、研修の効果を最大化する鍵となるでしょう。
【執筆者情報】
ビジネスゲーム研究所 米澤徳晃
研修会社に入社後、研修営業、研修講師業に従事。その後、社会保険労務士法人で人事評価制度の構築やキャリアコンサルティング活動に従事。その後、独立。講師登壇は年間100登壇を超え、講師としてのモットーは、「仕事に情熱を持って、楽しめる人たちを増やし続けたい」という想いで、企業研修を行っている。